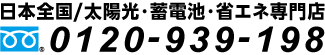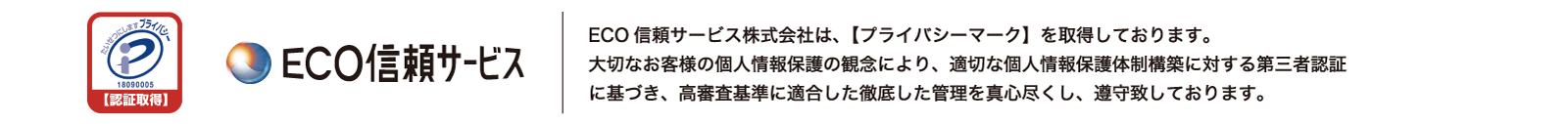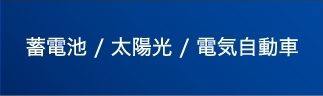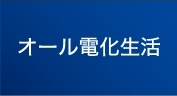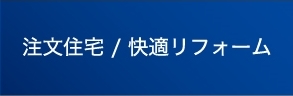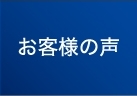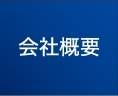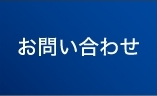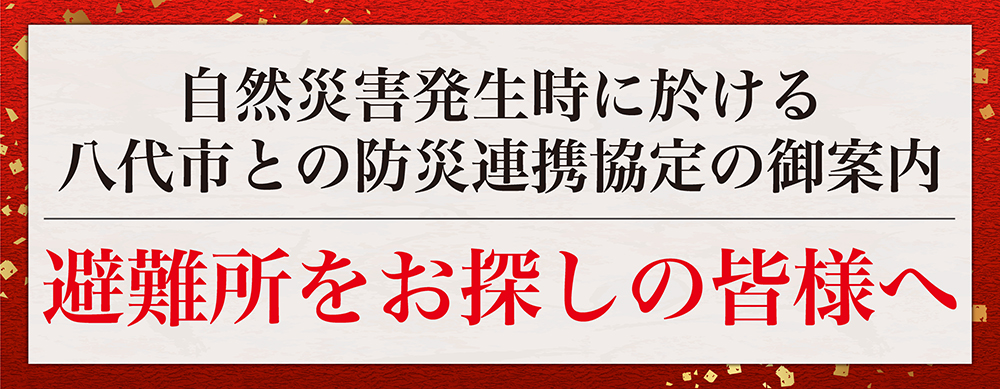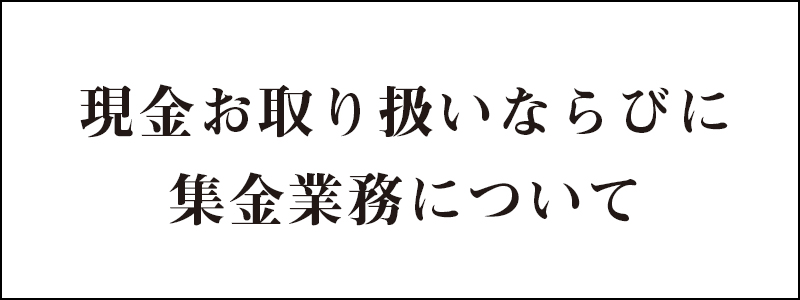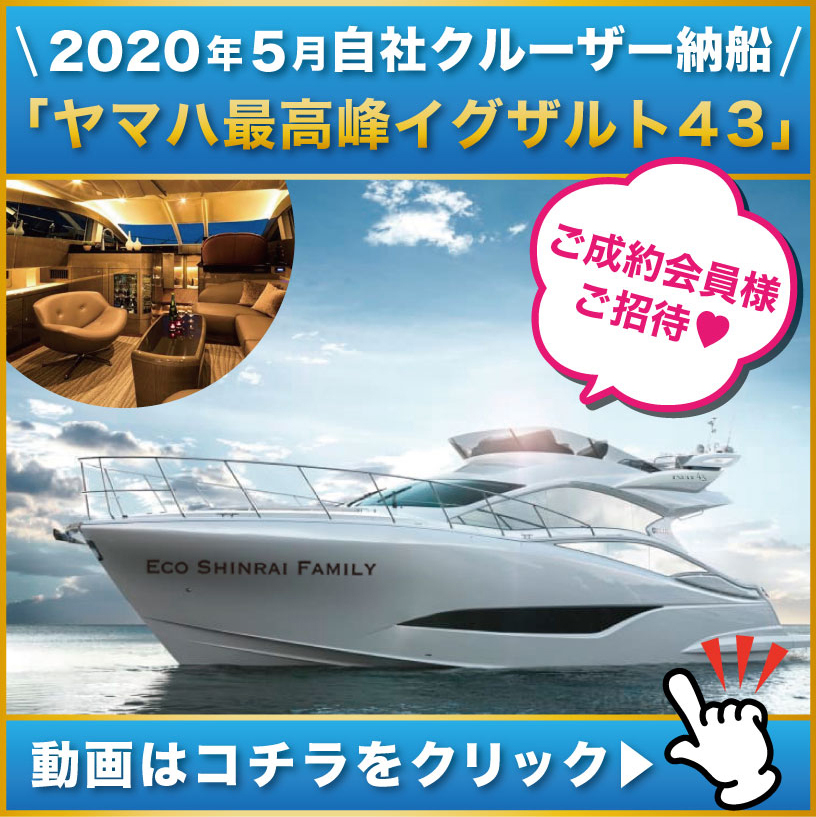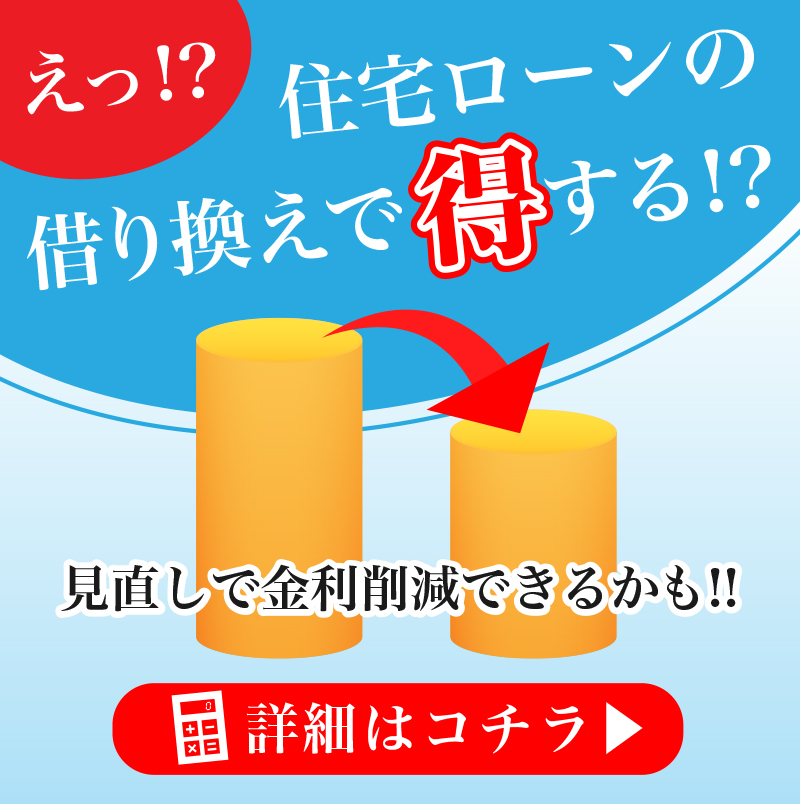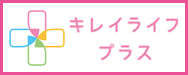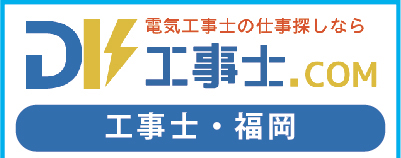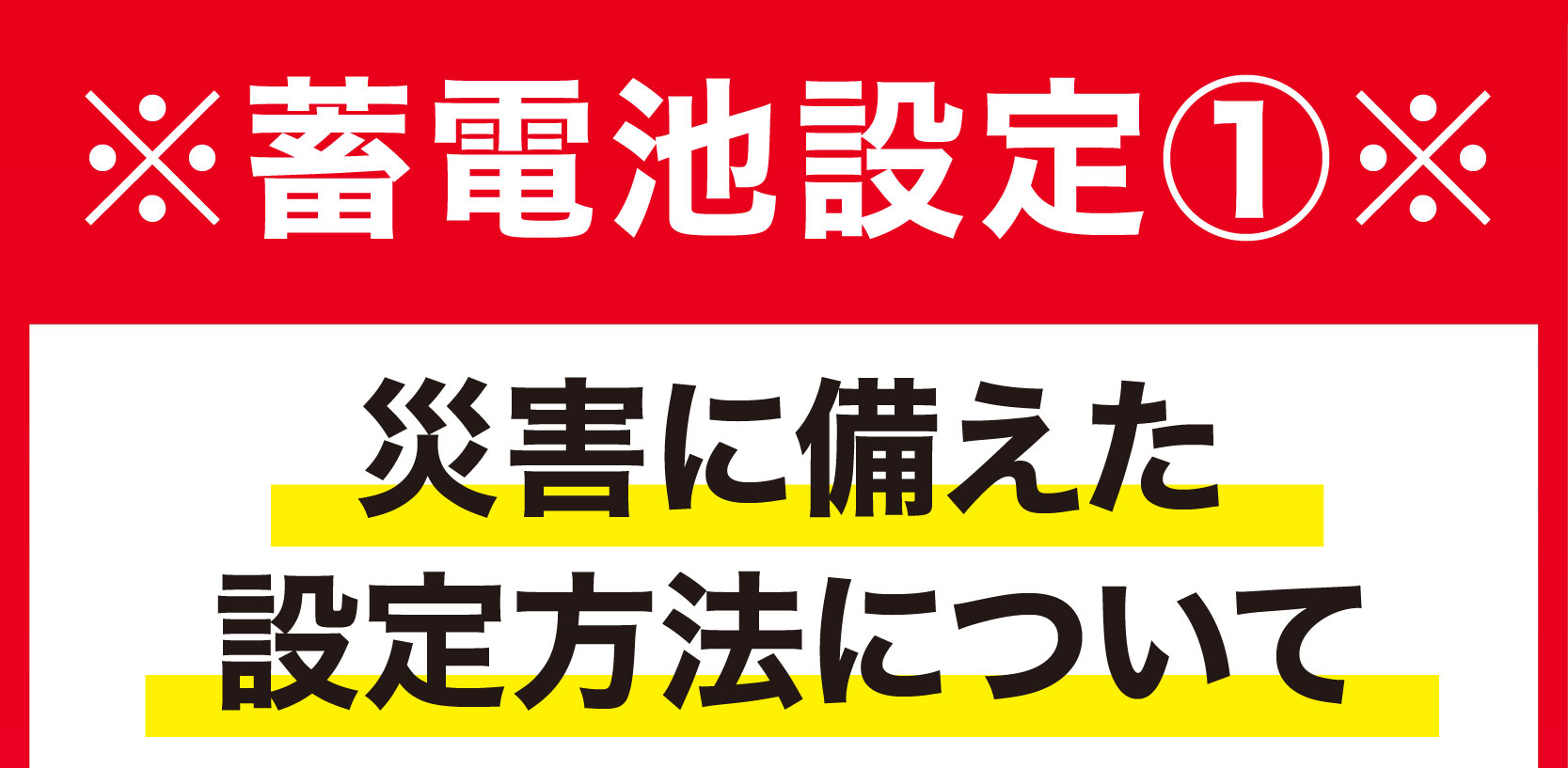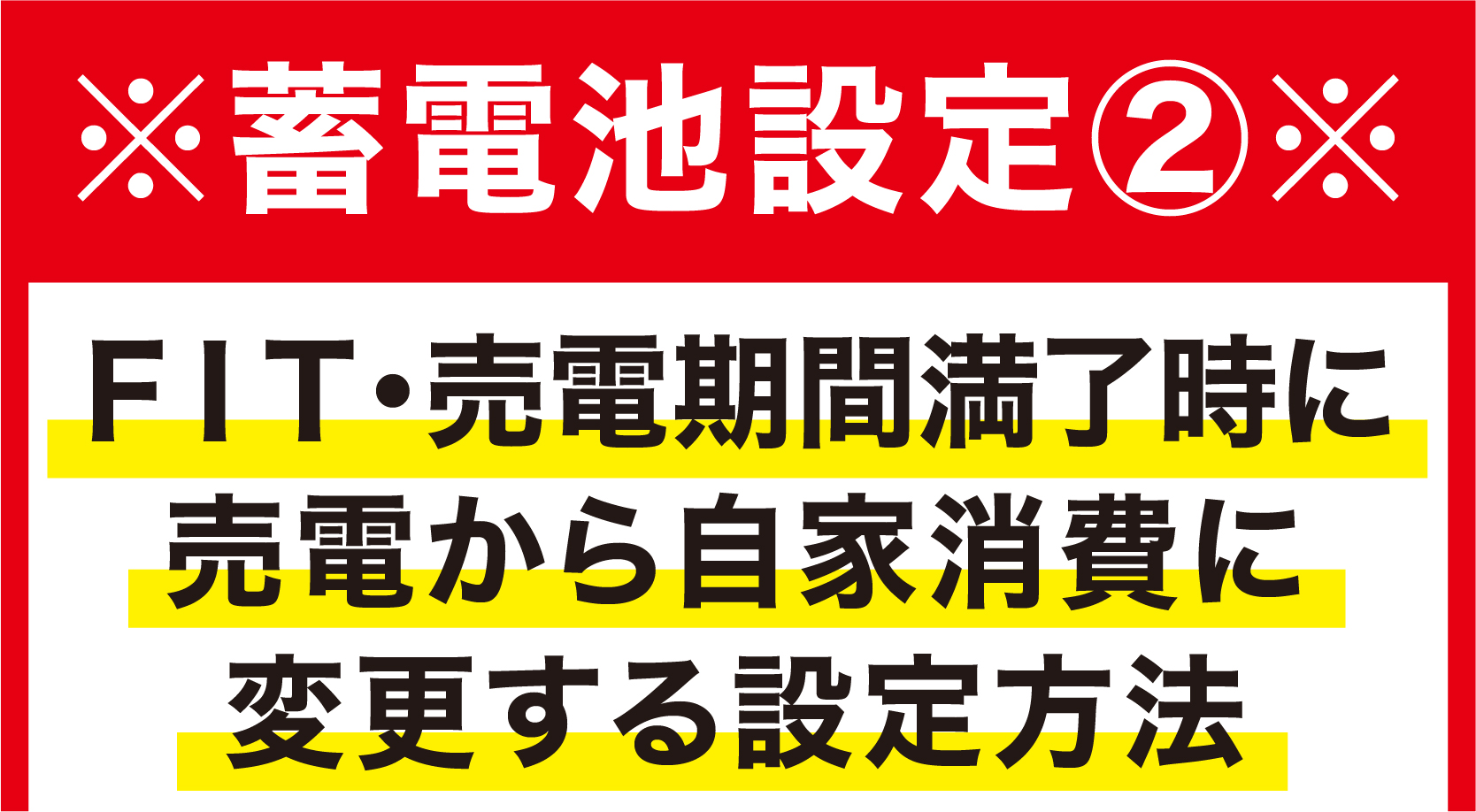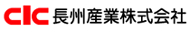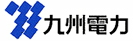- ホーム
- インフォメーション
-
2023.01.13
中部電力ら、広島で5.27MWの木質バイオマス発電着工 25年5月稼働
中部電力(愛知県名古屋市)など7社が共同出資する福山バイオマス発電所合同会社は1月6日、発電出力52,700kWの木質バイオマス専焼発電所「福山バイオマス発電所」(広島県福山市)の建設工事に着工した。2025年5月の運転開始を目指す。
想定年間発電電力量は約3.8億kWh。同発電所の燃料には木質ペレット、木質チップ(中国地方産の未利用間伐材等)の利用を予定している。
記事内容へ -
2023.01.12
兵庫に77MWの太陽光発電施設が竣工 ENEOS・関電が出資
パシフィコ・エナジー(東京都港区)は1月6日、兵庫県赤穂郡で開発を進めてきた太陽光発電所「播州メガソーラー発電所」(発電容量約77MW、直流ベース)を竣工した。なお、同事業を運営する合同会社は、関西電力(大阪府大阪市)とENEOS(東京都千代田区)が折半出資している。
同発電所の発電出力は62,880kW(太陽電池の合計出力は76,802kW)で、固定価格買取制度の認定(FIT認定)を受けた太陽光発電所では関西で3番目の規模になるという。想定年間発電量は約9300万kW。売電価格は15.37円/kWhで、2022年の卸売電力の平均価格22.43円/kWh(JEPXのシステムプライススポット価格)を大きく下回る。
記事内容へ -
2023.01.11
オムロン、再エネの「自己託送」開始 太陽光発電+NAS電池活用
オムロン(京都府京都市)は1月6日、自社事業所に対し、敷地外に設置した太陽光発電所から「自己託送」方式により再エネ電力を送電する取り組みを同月から開始したと発表した。自己託送による送電はオムロングループとして初めて。
この取り組みは、オムロングループで、環境ソリューションやエンジニアリング・サービスを提供するオムロン フィールドエンジニアリング(OFE/東京都目黒区)が、京都府宮津市内の遊休地(スキー場跡地)に新設した「オムロン宮津太陽光発電所」(パネル容量:734kW)で発電した電力を、約100km離れた自社事業所の京阪奈イノベーションセンタ(京都府木津川市)に送電、供給するもの。
オムロンは、これより年間200トン以上の温室効果ガス(GHG)排出量の削減を見込んでいる。
記事内容へ -
2023.01.10
政投銀、米・再エネファンドに出資 蓄電池・CCS・グリーン水素も対象
日本政策投資銀行(DBJ/東京都千代田区)は1月5日、米国Excelsior Energy Capital(EEC)が設立した、米国再生可能エネルギー事業を投資対象とする「Excelsior Renewable Energy Investment Fund II(エクセルシオール2号ファンド)」への出資を決定したと発表した。
米国では2022年8月にインフレ抑制法が成立した。同法には、エネルギー安全保障や気候変動への対策に3,690億ドルを投じることが盛り込まれており、これにより再生可能エネルギー市場の一層の拡大が予想されている。こうした中、同ファンドは太陽光や風力発電プロジェクトに加え、昨今国内外で注目を浴びる蓄電池、CCS(CO2回収・貯留)、グリーン水素等のトランジションや脱炭素化に資する新分野のプロジェクトも投資対象としている。
DBJはこれまでも国内外における再エネ分野での取り組みを支援してきた。DBJは、同ファンドによる再エネ事業への出資を通じて、米国における最新の業界動向や新分野における知見を獲得し、引き続き日本のエネルギー産業の発展と脱炭素社会の実現に貢献していく考えだ。
記事内容へ -
2023.01.09
日本海ガス、EVスマート充電の実証実験 メーカーの異なる車両・機器で
日本海ガス絆ホールディングス(富山県富山市)と日本海ガス(同)、アークエルテクノロジーズ(AAKEL/福岡県福岡市)の3社は、2022年12月26日、日本海ガスの社有車である電気自動車(EV)3台を活用し、EVスマート充電サービスの実証事業を開始すると発表した。
実証では遺伝的アルゴリズムを活用したEV充電マネジメントシステムを活用し、技術的難易度が高いとされる複数社メーカーの異なる「EV車両・充電器・通信制御プロトコル」を組み合わせた遠隔制御自動充電を同時に運用。系統の制約やEV充電状態に応じて充電量をコントロールする。EV充電を最適化し再エネを最大活用するソリューションの構築を目指すとしている。
記事内容へ -
2023.01.08
キリンHD、脱炭素への「移行」ローンで500億円調達 国内食品企業初
キリンホールディングス(東京都中野区)は2022年12月26日、国内の食品企業として初めて、温室効果ガス(GHG)排出量ネットゼロ達成に向けた「トランジション・リンク・ローン」により500億円を調達すると発表した。借入時期は2023年1月、期間は10年間。
調達した資金は、同社がScope1、2のGHG排出量削減に向けた取り組みとして推進する省エネ、再エネ関連のプロジェクトに充当する予定だ。同ローンについては、経済産業省による2022年度「温暖化対策促進事業費補助金」と産業競争力強化法に基づく成果連動型利子補給制度(カーボンニュートラル実現に向けたトランジション推進のための金融支援)が適用される。
記事内容へ -
2023.01.07
トヨタラグビーチーム、公式試合に再エネ電力を活用 中電ミライズが協力
トヨタ自動車のラグビーチームであるトヨタヴェルブリッツ(愛知県豊田市)は12月28日、中部電力ミライズ(同・名古屋市)、豊田市と共同で、試合運営に必要な電力を再エネで賄うカーボンニュートラルマッチを開催すると発表した。
今回のカーボンニュートラルマッチは2023年1月8日、豊田スタジアムで開催される「JAPAN RUGBY LEAGUE ONE」の第3節「トヨタヴェルブリッツVSブラックラムズ東京」で実施される。
記事内容へ -
2023.01.06
東急不動産とシン・エナジーが資本業務提携 再エネ発電所の開発を強化
東急不動産(東京都渋谷区)と全国で再生可能エネルギー発電所の開発を手掛けるシン・エナジー(兵庫県神戸市)は、2022年12月23日付で、資本業務提携を行うことで合意した。再エネ電源の開発力強化を目的としたもの。同日付で、東急不動産がシン・エナジーの株式(普通株式)を一部取得した。
今回の提携に基づき、今後、両社が持つ経営資源を組み合わせることで、スピード感を持った再エネ事業の領域拡大、脱炭素社会への貢献を目指す考え。
記事内容へ -
2023.01.05
自然電力とNTTグループ、エネマネ領域で提携 EVスマート充電サービス等
NTTアノードエナジー(東京都港区)と自然電力(福岡県福岡市)は、IoT/AI技術によるエネルギーマネジメント領域で業務提携する。第一弾として2023年3月から、電力のピークカット・ピークシフトにより電気料金を削減できる「電気自動車(EV)スマート充放電サービス」の提供を開始する。
同サービスでは、自治体・法人の高圧電力施設に太陽光発電設備とEV充放電器(V2B/Vehicle to Building)を設置し、ビルのピーク消費電力予測と太陽光発電予測を用いてピークカットが必要な日・時間を予測、消費電力を制御する。これにより電力料金を削減する。また、大規模自然災害時には太陽光発電施設からEVへ充電することで、レジリエンスを強化する。なお、同サービスは、2022年9月からNTT西日本山口支店の協力を得て共同開発・実証に取り組んできたもの。
記事内容へ -
2023.01.04
損保ジャパン、太陽光発電事業者向けの新サービス 構造設計を評価
損害保険ジャパン(東京都新宿区)は12月26日から、太陽光発電事業者向けの新サービスを開始する。SOMPOリスクマネジメント(同)、構造耐力評価機構(大阪府松原市)と協力し、太陽光発電設備の構造設計評価と、設計上の問題が明らかになった場合に設備の安全性を再構築する支援サービスを提供する。損保ジャパンの調べによると保険業界として初めての取り組みだという。
構造設計評価(構造設計書のレビューサービス)の対象設備は、太陽光発電設備(設備容量不問)で、対象となるリスクは風災・雪災・水災。太陽光発電設備の構造設計について、構造関係の法令等と照らして、風災や雪災などの自然災害リスク に対する構造計算の妥当性を確認・評価する。事故が発生している設備については、事故と設計の因果関係と、事故が再発する可能性についても評価する。
記事内容へ