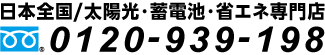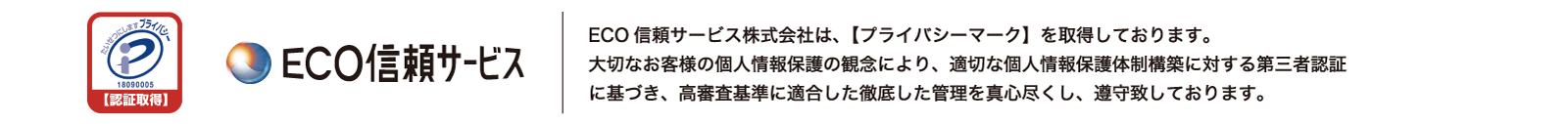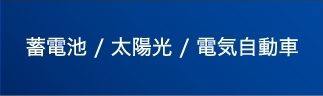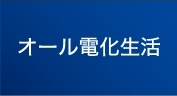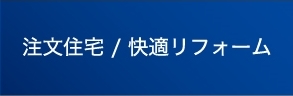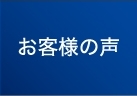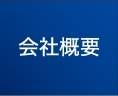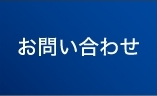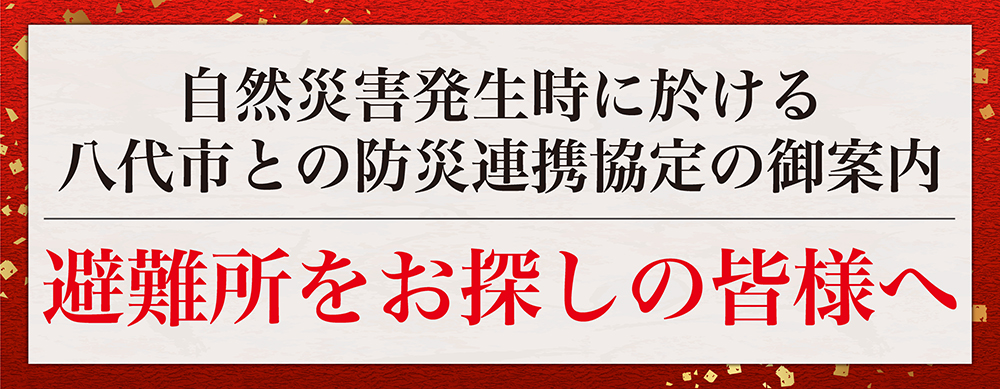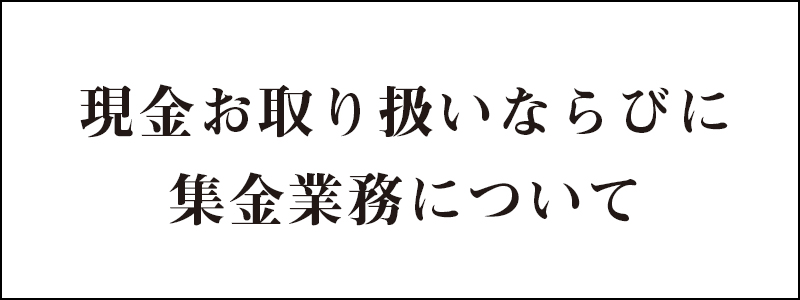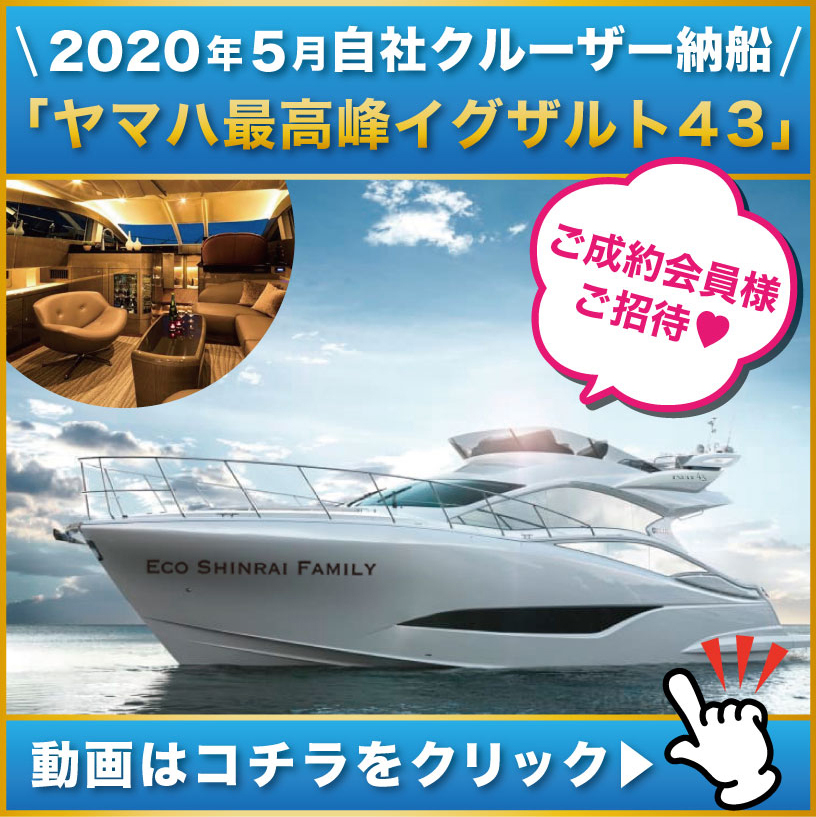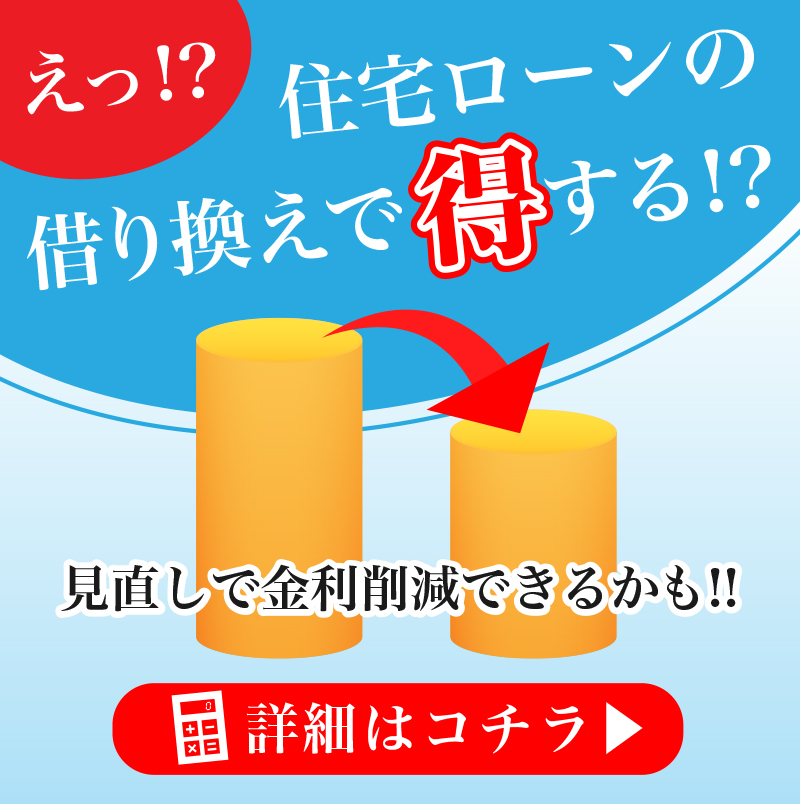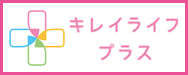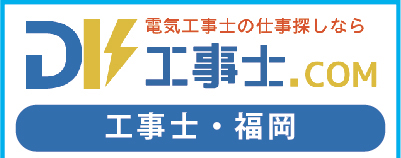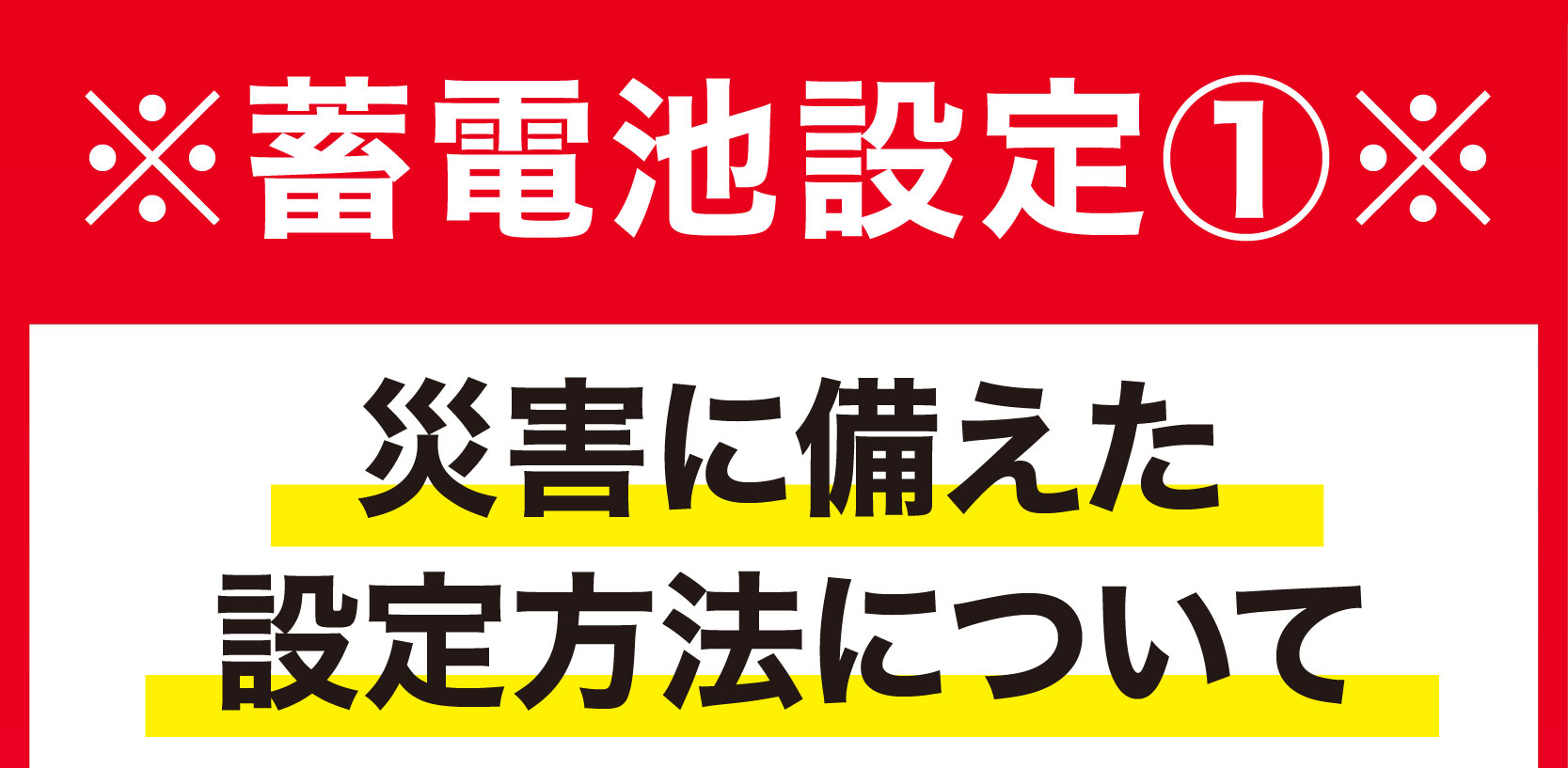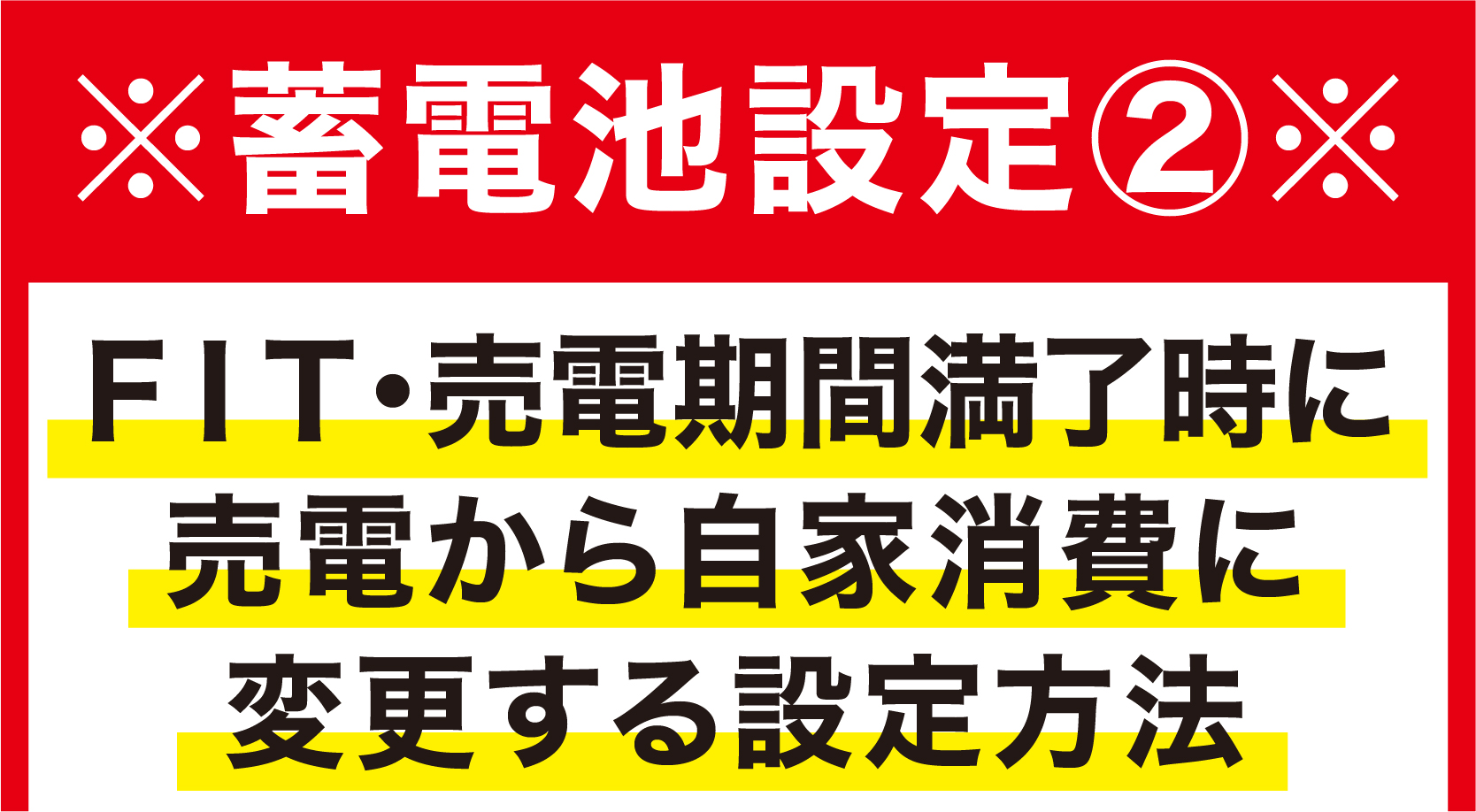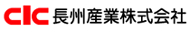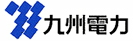- ホーム
- インフォメーション
-
2023.07.16
国内初のブルー水素・アンモニア製造・利用一貫実証で地上プラントの建設開始
INPEX(東京都港区)は7月12日、新潟県柏崎市で推進する「ブルー水素・アンモニア製造・利用一貫実証試験」プロジェクトにおいて、地上プラント設備の建設工事を開始したと発表した。
年間700トン規模の水素製造設備やCO2の地下圧入設備など
同実証試験は、国産の天然ガスを用いたブルー水素・アンモニアの製造、国内枯渇ガス田でのCO2回収・利用・貯留(CCUS)、さらに発電による利用までを一貫して実証する日本初のプロジェクトだ。
記事内容へ -
2023.07.15
丸紅、カナダで大規模商用化を目指すCCS事業に参画 年間300万トン規模
丸紅(東京都千代田区)は7月13日、カナダ・アルバータ州において、CO2回収・貯留(CCS)事業へ参画すると発表した。同州でCCS事業を開発中のBison Low Carbon Ventures(Bison社)と株式引受契約を締結した。
Bison社が主導するMeadowbrook CCSプロジェクトは、世界有数の大型CCS事業の構築を目指している。同州・エドモントン近郊に位置し、アルバータ工業地区など近隣の産業から排出されるCO2の輸送・貯留を予定。
記事内容へ -
2023.07.14
苫小牧で再エネ水素供給網構築へ、実証事業 スパークス・グループら
スパークス・グループ(東京都港区)は7月10日、子会社のスパークス・グリーンエナジー&テクノロジー(SGET/同)を通じて、北海道苫小牧市で再生可能エネルギー由来水素の製造・貯蔵・輸送・利用までのサプライチェーンを構築する実証事業を開始すると発表した。
廃棄物発電+太陽光発電の電力で年間最大100万Nm3再エネ水素を製造
環境省事業の採択を受け、苫小牧市、基礎化学品メーカーの北海道曹達(苫小牧市)、自動車部品メーカーのトヨタ自動車北海道(同)、FA機器商社の明治電機工業(愛知県名古屋市)とともに実施する。
記事内容へ -
2023.07.13
住友林業傘下の森林ファンドに10社が出資 約600億円、クレジット創出
住友林業(東京都千代田区)は7月10日、傘下で米国の森林アセットマネジメント事業会社Eastwood Forests(EF社)が、主に北米で森林を購入し運用する森林ファンドを組成し運用を開始したと発表した。
同ファンドはカーボンクレジットのマーケットや制度が先行している米国で木材販売とカーボンクレジットの創出・販売を行う。ENEOS(東京都千代田区)、大阪ガス(大阪府大阪市)、ユニ・チャーム(東京都港区)など日本企業10社が出資した。資産規模は約600億円で運用期間は15年間。
記事内容へ -
2023.07.12
伊藤忠子会社、農業分野の温室効果ガス削減量をNFT化 実証実験
伊藤忠テクノソリューションズ(CTC/東京都港区)は7月7日、新潟大学と共同で、新潟市の農地(約60アール)における温室効果ガス(GHG)の放出量について、正確な測定やデータの可視化に関する実証実験を開始したと発表した。同社では将来的なカーボン・クレジットとしての取引を目指し、GHG放出量の削減に貢献した生産者の活動実績のNFT化(代替不可能なデータ)も進める。
GHG放出量削減に繋がる生産者の活動実績をNFT化し取引
実証実験の期間は2023年6月~2024年3月。主に以下の3点に取り組む。
記事内容へ -
2023.07.11
三井物産、欧州・低炭素メタノール製造事業に出資 グリーン水素・CO2合成
三井物産(東京都千代田区)は7月6日、デンマークにおいて、グリーン水素とグリーンCO2から合成して作る低炭素メタノール(e-メタノール)を製造・販売する事業に出資参画すると発表した。
同事業は、出力304MWの太陽光発電、水電気分解、メタノールの各設備からなる「e-メタノール」製造工場の建設を進める。同工場のe-メタノールの年産能力は最大4.2万トンで、商業規模で製造する世界初・世界最大の事業だという。2024年からe-メタノール製造を開始する予定で、デンマークの海運大手A.P.モラー-マースク社、玩具大手レゴ社、医薬品大手ノボノルディスク社への販売契約を締結済み。
再エネ由来電力を活用して製造するグリーン水素と、バイオマス由来のグリーンCO2を合成
記事内容へ -
2023.07.10
大東建託、再エネ拡大へ「朝来バイオマス発電所」取得 24年度中に再稼働へ
大東建託(東京都港区)は7月6日、関電エネルギーソリューション(大阪府大阪市)、兵庫県森林組合連合会(兵庫県神戸市)と、朝来バイオマス発電所およびbe材供給センターの事業譲渡契約を締結したと発表した。今後は現在、発電を停止している同バイオマス発電所の再稼働を目指す。
バイオ発電導入により、再エネの国内導入率50%へ
記事内容へ -
2023.07.09
東京ガスら、廃熱回収装置内蔵バーナの水素専焼実現 アルミ製造等脱炭素化へ
東京ガス(東京都港区)、東京ガスエンジニアリングソリューションズ(TGES/同)、正英製作所(大阪府大阪市)は7月5日、日本で初めて、水素燃焼が可能な廃熱回収装置内蔵水素バーナを開発したと発表した。
水素専焼を実現し、燃焼時のCO2排出量をゼロにすることで、アルミ製造等の高温熱分野の脱炭素化に貢献する。このバーナは正英製作所が10月から販売を予定している。
記事内容へ -
2023.07.08
新車販売電動車100%へ BEVの車両価格低減・普及の課題は?
目標の新車販売電動車100%にはBEV・HEV・PHEV・FCEVが含まれる。CO2削減にあたってはBEVの普及がカギとなるが、解決の難しい3つの課題とは何か。またBEV以外の電動車の可能性にはどのようなものがあるのか。大手自動車部品サプライヤーデンソーで、全社プロジェクトなどを歴任している鈴木 万治氏に聞いた。
BEV普及の課題とは
CO2削減にあたっては電気自動車(BEV:Battery Electric Vehicle)の普及が鍵だとされています。それが実現できればよいのですが、私は、解決の難しい3つの課題があると考えています。
記事内容へ -
2023.07.07
IHI、石油製品製造時のCO2を樹脂原料製造に活用 タイで実証実験
IHI(東京都江東区)は7月4日、タイの石油化学プラントで、カーボンニュートラルな低級オレフィン合成技術の実証を開始すると発表した。石油製品の製造工程で発生するCO2を、樹脂原料製造へ活用する。実証期間は2026年3月まで。
タイ王室系企業The Siam Cement Group傘下のSCG社との間で、SCGCが運営する同国の石油化学プラントにおいて、「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/CO2排出削減・有効利用実用化技術開発/CO2を原料とした直接合成反応による低級オレフィン製造技術の研究開発」の実証試験を実施することで合意した。
一日当たり100kgのCO2を注入する小型スケールでの実証を行う
記事内容へ