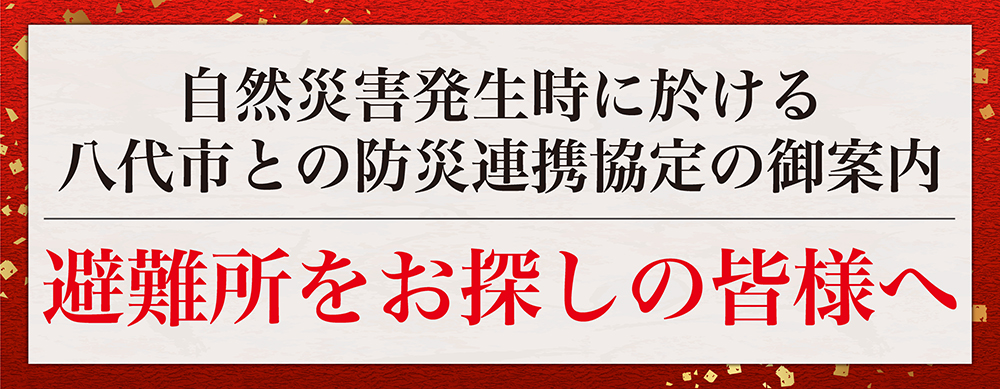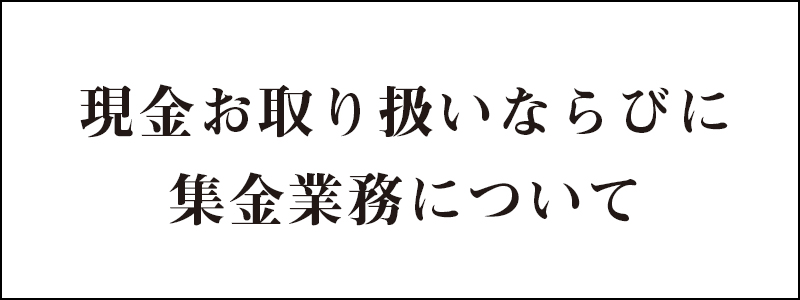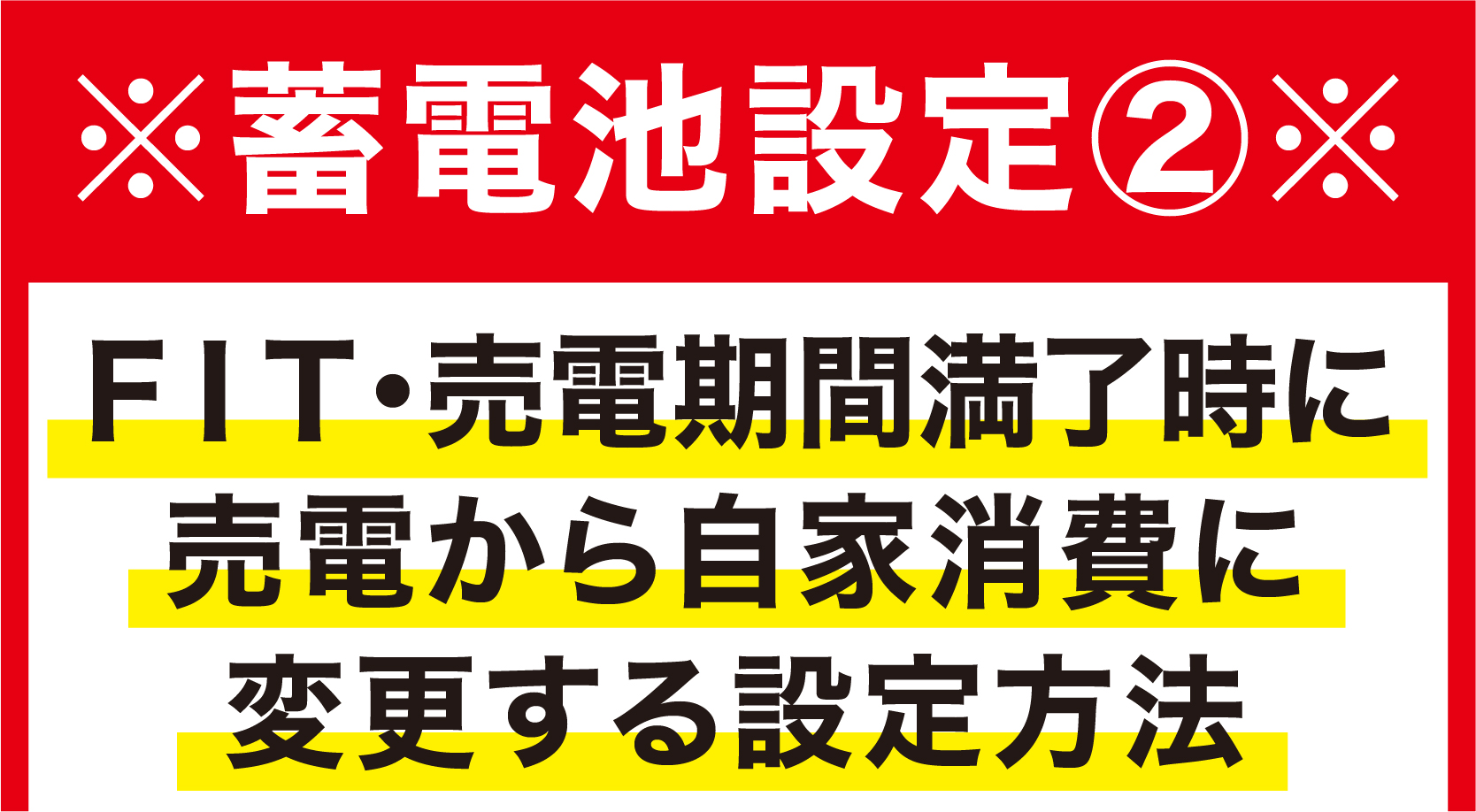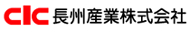- ホーム
- インフォメーション
-
2019.01.30
CO2ゼロ電気、中電7月販売 水力・太陽光で発電
中部電力は七月から、水力や太陽光など二酸化炭素(CO2)を出さないエネルギー源で発電した「CO2フリー電気」を中部地方の企業や一般家庭に販売する。通常の電気代より割高に設定するが、CO2削減を求められる企業や、環境問題への意識が高い消費者の需要に応える。
CO2フリーの電気は、自社の水力発電所の発電分に加え、十一月以降、再生可能エネルギーを高く売電できる「固定価格買い取り制度」の期限が切れた家庭用太陽光の電気を購入してまかなう。原発の電気は取り扱わない。料金設定の詳細は四月ごろ決める。販売が広がれば、収益を再エネ事業への投資に振り分けることも念頭に置く。
同社のアンケートでは、一般の二割弱が「高くても環境に優しい電気を使いたい」と回答。実際の購入につながるかは未知数だが、今回の販売を通じてニーズを測る。一方、企業が排出するCO2削減は世界的な要請で、「需要は確実に見込める」(中電幹部)という。同様のCO2フリー電気は東京電力や四国電力、一部の新電力が販売している。
記事内容へ -
2019.01.29
“太陽光2019年問題”着地点はどうなる?
いまエネルギー関係者の間で注目されているのが、「太陽光2019年問題」の帰趨。再生可能エネルギーを利用促進するため、一般家庭に太陽光パネルを設置して発電させ、余った電力を10年間固定価格で買い取るという制度が、今秋から期間満了に伴い順次終了する。導入した160万超の家庭は、結局得をするのか損するのか? 環境・エネルギー問題に詳しいコンサルタントが、目下の状況と着地点について解説する――。 再エネ利用促進のため、国策で高水準の買取価格が10年間保証された太陽光発電。(写真=山本つねお/アフロ)
再エネ利用促進のため、国策で高水準の買取価格が10年間保証された太陽光発電。(写真=山本つねお/アフロ)相場より遥かに高かった買取価格
地球温暖化対策から世界中で「脱炭素化」が進む中、日本では相次ぐ震災などの経験を経て、大規模災害に対する備えやエネルギー源の多様化を実現するため、再生可能エネルギー導入が促進されてきた。一般家庭の屋根に太陽光パネルが設置されている光景も、もはや珍しいものではない。
もっとも、家庭で太陽光発電をするとなると、それなりに大きなコストがかかる。環境問題や防災に対する意識が高いから、といった動機だけで経済的ハードルを超えられるものでもない。だからこそ、国は補助金などで導入支援をする施策も採ってきたが、中でも重要な役割を果たしてきたのが、家庭で発電され余った電力を電力会社が“高く”買い取る仕組みだ。
具体的には、2009年11月から「余剰電力買取制度」がスタート。当初の買取価格は住宅用(10kW未満)で48円/kWh、しかも10年間固定で買い取ってもらえるという内容だった。この価格を聞いて高いと思うだろうか、安いと思うだろうか。
「極めて高い価格です」――そう語るのは、国内外の環境・エネルギー問題に詳しい三菱総合研究所のシニアプロジェクトマネージャー・三浦大助氏だ。
「太陽光発電をしている家庭でも自家発電以外に電気を使いますから、その電気代は当然支払わなければなりません。しかし実際には、使用電気代として支払う金額より買い取り価格のほうが高いので、電力会社から届く請求書は『○○円を支払ってください』ではなく、実質的には『○○円を支払います』という内容になっている場合もあると考えればいいでしょう。それが丸々十年分ともなれば、小さな金額ではありません。そもそも大きな火力発電所の発電コストは、現在の相場観で石炭火力5~6円/kWh、ガス火力7~10円/kWh程度です。これと比べればいかに高水準での買取であるかがわかります」
また、現在の電気料金水準は家庭用の低圧電灯料金で、地域ごとに差はあるものの、平均21~23円/kWh程度であり、それと比べても、太陽光の買取単価はかなり高かったわけである。
余剰電力買取制度は、2012年7月から「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)」に引き継がれた。買取価格は年度ごとに見直され徐々に低減してきており、現在は住宅用(10kW未満)で26円/kWh。今後も引き下げられる見込みだが、太陽光発電システムの導入コストもどんどん下がってきているので、その変動幅は妥当な範囲といえるのかもしれない。
記事内容へ -
2019.01.15
4月から「ゼロエミッション・データセンター」建設に着手 22年までに「再生エネ100%」で稼働!
京セラコミュニケーションシステム(KCCS)は、北海道と石狩市の協力を得て、再生可能エネルギー100%で運営する「ゼロエミッション・データセンター」の建設に4月から着手する。2021年中の稼働開始を目指す。太陽光、風力、バイオマス発電を順次、連携させ、22年には再生エネルギー100%で稼働する。
太陽光発電モジュールや蓄電池、燃料電池、LED、EMS(エネルギー・マネジメント・システム)など京セラが培ってきた機器設計技術と、KCCSのソーラー発電所建設・保守などのノウハウ、予測制御AI(人工知能)の知見、データセンターの運用実績をバックボーンに、「ゼロエミッション・データセンター」で再エネ発電による電力供給とデータセンターの電力需要を一体運用する。
高い信頼性と安定した電力供給、電力コスト低減が求められるデータセンターを再エネ100%で運営することで、信頼性・安定性とともにコスト面でも事業が成立することを実証する考え。太陽光、風力、バイオマスで発電した電力を自営線で結び、発電所から電力を直接供給する。夏場は、冬に貯めた雪でサーバを冷却する雪氷冷房も備える。
実証で培ったノウハウをもとに、再エネ事業を多面的に展開し、24年に関連事業の売上高300億円を目指す。
記事内容へ -
2019.01.14
発電と農業の場所“シェア”始まる。太陽光発電の下でブドウ栽培

写真はブドウ畑のイメージ
千葉商科大学は、農地の上で太陽光発電を行う「ソーラーシェアリング」(営農型太陽光発電)を市川キャンパス(千葉県市川市)に導入する。太陽光で発電した電力を同キャンパスで自家消費しながら、発電パネルの下でブドウを栽培、将来はオリジナルワインに加工して販売する計画だ。再生可能エネルギーの啓発に役立てると同時に、農業関連ビジネスを実体験できる機会を学生に与えるなど教育の場としても活用していく。ソーラーシェアリングの設備は、同キャンパス内の運動場の一部を転用して1月をめどに設置する。当初は約330平方メートルの敷地に、太陽光パネル48枚を設置。出力は計8・64キロワットと微量ながら、学内の消費電力の一部に利用する。太陽光発電パネルは高さ約3メートルの架台の上に設置し、その下の空間でブドウを栽培する。3年目以降にブドウの収穫を本格化してワインを造る。ワインの醸造は山梨県内の醸造会社に委託することを想定している。
ワインの商品化プロジェクトには学生が参加する。今春に学内から参加学生を公募してチームを立ち上げ、ブドウの栽培からワインの商品企画、販路開拓まで学生が主体となって取り組む予定だ。
千葉商科大は千葉県野田市に最大出力2・9メガワットのメガソーラー(大規模太陽光発電設備)を保有。大学の消費エネルギーと大学がつくるエネルギーを同等にする「自然エネルギー100%大学」を目指しており、今回はその一環となる。原科幸彦学長は「新しい発電形態を大学で実践してみせることで、再生可能エネルギーの普及拡大に貢献したい。日本の次世代農業の担い手の育成にも結び付けたい」と話している。
記事内容へ -
2019.01.12
太陽光発電 住宅向けの活用を続けたい
住宅向けに普及した太陽光発電設備をどう活用し続けていくか。官民で知恵を絞りたい。
家庭などで余った太陽光発電の高値買い取りが今年11月から順次終了する。2009年にスタートした「余剰電力買い取り制度」が、10年の適用期限を迎えるためだ。
太陽光パネルの耐用年数は20年以上とされる。まだ十分に発電できる太陽光設備を有効利用していくことが求められる。
太陽光発電を巡っては12年に当時の民主党政権が、事業者による太陽光発電の「全量」を高値で買い取る制度を始めた。
これに事業者が殺到し、買い取り費用を賄うために電気料金が高騰する弊害を招いた。
一方、住宅向けは、家庭で使い切れなかった「余剰分」を電力会社が買い取るため、電気料金の押し上げ効果が相対的に小さい。太陽光発電の着実な普及に一定の役割を果たしたと言えよう。
買い取り期間の終了は、11~12月だけで53万件、23年までに165万件に上る。1キロ・ワット時当たり最高48円だった買い取り価格も10円弱に下がる見込みという。
買い取り期間を過ぎた太陽光発電を、国内自給できるクリーンな電源として生かしたい。
ただし、課題も多い。
何も対応しないまま買い取り期間が終わると、家庭の余剰電力は無償で電力会社に送電され、収益機会を逃すことになる。
電力各社の送配電網には、契約外の電気が流れ込み、電力需給調整が難しくなるという。こうした事態を避けるには、新たな売電契約を結ばなければならない。
現在電気を売っている契約者には、電力会社から期間終了の半年ほど前に通知が届く。これを見逃さないことが重要だ。
蓄電池を購入し、好天時に発電した電気を貯め、夜などに使い切る方法もある。電気代が安くなるほか、災害時の備えにもなる。
だが、蓄電池の設置費用は一般的に200万円程度と高い。幅広く普及させるには、安価な蓄電池の開発が欠かせない。
懸念されるのは、買い取り終了後の「ゼロ円売電」をことさらに強調し、高価な蓄電池の購入や新たな売電契約の締結を迫る営業が横行しかねないことである。
売電できる事業者は複数ある。どのような対応が最も得なのか慎重に見極めることが大切だ。
経済産業省や消費者庁は業界の動向を監視し、事業者や家庭への注意喚起に努めるべきだ。
記事内容へ -
2019.01.11
太陽光、全道停電で貢献 買い取り価格下落、売電の継続課題
2018年9月に発生した胆振東部地震と全道停電の際、住宅の太陽光発電設備を電力会社の送電網から切り離した上で稼働させる「自立運転」に切り替え、電気を自ら賄った家庭も多かった。太陽光発電協会(東京・港)が地震後に道内で実施した調査では、蓄電機能併設の太陽光をもつ家庭でほぼ全戸、蓄電機能がない家庭でも約85%が電気を自家消費した。
記事内容へ -
2019.01.10
事業用太陽光22%安く 19年度、買い取り価格14円に
経済産業省は再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度(FIT)で、2019年度の太陽光発電(事業用)の価格を1キロワット時あたり14円とし、現在の18円から22%下げる。安い価格で発電する事業者から順番に買い入れる「入札制」の対象も出力500キロワット以上と、従来の2千キロワット以上から広げる。コスト重視を徹底するが、普及との両立が課題になる。
記事内容へ -
2018.12.28
AI使い、スマート家電からスマートホームへ
パナソニック、シャープといった家電メーカーが、あらゆるモノがネットにつながる「IoT家電」の投入を本格化させている。インターネットに接続するだけでなく、連携する人工知能(AI)が、利用者一人一人の生活を学習して暮らしを助けるよう高機能化が進められている。異なるメーカー同士の機器連携も進む。ただ、現状では通信機能のない家電を使っている人が多く、機能がある家電を持っていても使用していない人は多い。普及に向けて通信機能を使う気になってもらうための工夫も必要だ。(織田淳嗣)
省エネから暮らし向上へ
東日本大震災後の省エネ需要の高まりで、家電に先行して、住宅設備へのネット接続機能が浸透していった。住宅メーカーは自家発電などですべてをまかなう「ゼロエネルギー住宅」(ZEH=ゼッチ)を実現する手段として、家庭向けエネルギー管理システム(HEMS=ヘムス)の販売を本格化。太陽光パネル、蓄電池などさまざまな機器が接続して効率的な運用を行い、エネルギーを管理して電気代を減らす。
記事内容へ -
2018.12.27
東京・母島を再エネ100%で運用、2019年からプロジェクトが本格始動
東京・小笠原諸島に位置する母島(ははじま)で、島で利用するエネルギーを100%再生可能エネルギーに切り替えるプロジェクトが始動した。2018年12月21日に東京都と小笠原村が、東京電力パワーグリッドと実証実験の実施について協定を結んだ。太陽光発電や蓄電池などの設備を導入して、2022年度末から運用検証を開始する計画だ。
環境先進都市を目指す東京都では、環境施策の1つとしてCO2を排出しない「ゼロエミッション・アイランド」の実現を掲げている。今回の取り組みはこうした東京都の方針と、小笠原村が目指す自然と調和した「サステイナブルアイランド」の実現に寄与するものだ。東京都の小池都知事は2018年7月1日に小笠原諸島(小笠原村)返還50周年を記念して母島で開かれた式典で、今回のプロジェクトの実施を表明していた。
母島は面積約20平方キロメートルの島で、人口は約500人。現在は島の南部にある最大出力960kW(キロワット)のディーゼル発電所「母島内燃力発電所」が主な電力源となっている。
今回の実証実験では、島内の複数箇所に太陽光発電設備とを設置。さらに出力変動に対応するために、定置型の蓄電池システムも導入する計画だ。これらの設備を運用し、当面は島内で利用する電力を、1年のうち半年程度を太陽光発電からの供給のみで賄うことを目指す方針だ。
発電設備や蓄電池は世界自然遺産区域を避け、都有地や村有地などに設置する方針だ。設置にあたっては、自然環境調査を実施し、小笠原村の自然環境専門家の意見なども取り入れながら、自然環境や景観に影響を与えないように慎重に進めるとしている。
具体的なスケジュールは、2019年1月から自然環境調査を開始し、2022年度末から設備の運用検証を始める。実証機関は3年間の予定だ。ただし、3年間が経過した後も、太陽光発電による電力供給を継続し、さらなる再生可能エネルギー発電設備の導入拡大を図るとしている。
記事内容へ -
2018.12.26
九州の新電力、7割が卒FITに関心
新電力の会員組織である「日経エネルギーNext ビジネス会議」の呼びかけで、九州を営業エリアとする新電力39社が今後の九州市場について議論した。再生可能エネルギーの普及が全国でもっとも進んでいる九州。再エネに商機を見いだす新電力が多い。
「スイッチングの際、大手電力による『取り戻し営業』に遭ったことは?」との問いに、「ある」という回答数が59%、「ない」が25%、「分からない」が16%だった。
福岡市で12月10日に開いた日経エネルギーNextビジネス会議九州分科会には、39社から59人が集まった。スマホで投票できるアンケートツールを使い、集まった参加者にその場で回答してもらった結果だ。
取り戻し営業は、需要家が新電力にスイッチングの意思を示してからスイッチングが完了するまでの2カ月の間に、大手電力が安値を提示してスイッチングを阻止することを指す。送配電部門に通知されるスイッチング情報が小売部門に流れている可能性などが指摘され、現在、電力・ガス取引監視等委員会が規制する方向でルールの検討が進んでいる。
取り戻し営業は大手電力からの需要家の離脱率が大きい関西エリアなどで特に大きな問題になった。アンケートの結果は、九州エリアでも九州電力による“取り戻し”が相当程度あったことを物語る。
今回の九州分科会は、定期的に東京で開催している新電力による会合の九州版を、九州を営業エリアとする事業者に呼びかけて実施した。
この日の議論は今後の九州市場をどう展望するかを中心に展開した。
「(九州市場も)今後はガスとのバンドルがポイントになるのではないか」。全国展開している通信系新電力幹部から問いかけがなされた。
これに対して他の参加者からは、「顧客目線で考えるとワンストップのエネルギーサービスが求められる可能性は大いにある。将来は(ガスも)必要だろう」(関西系新電力幹部)、「商材の1つとしてそろえておきたい。地域のガス会社と組むことを考えたい」(南九州エリアに本社を置く新電力幹部)といった声が上がった。
記事内容へ