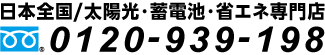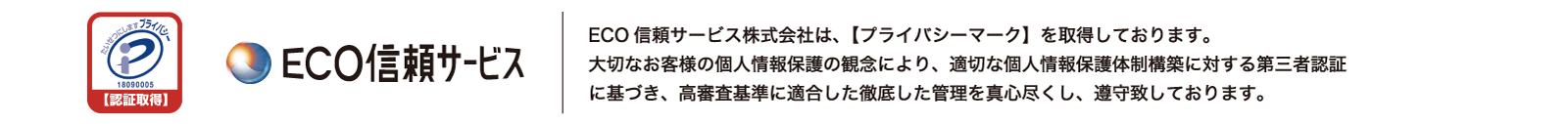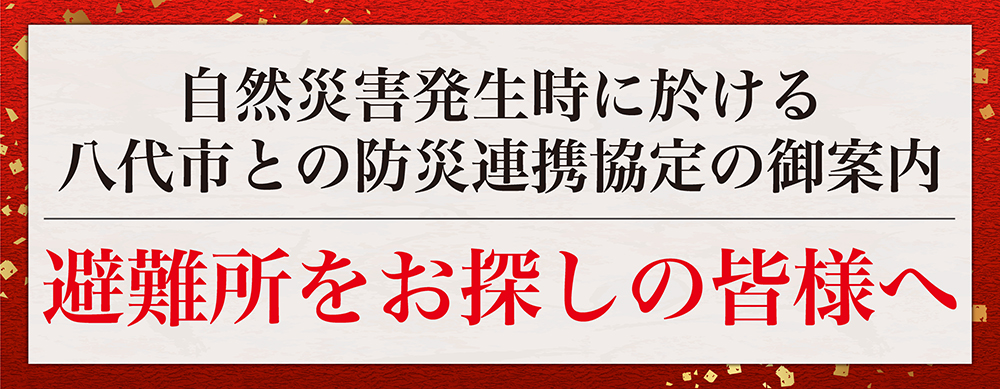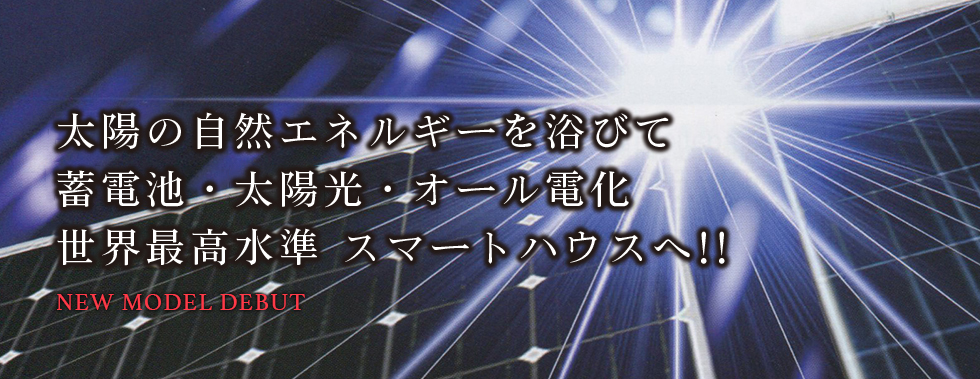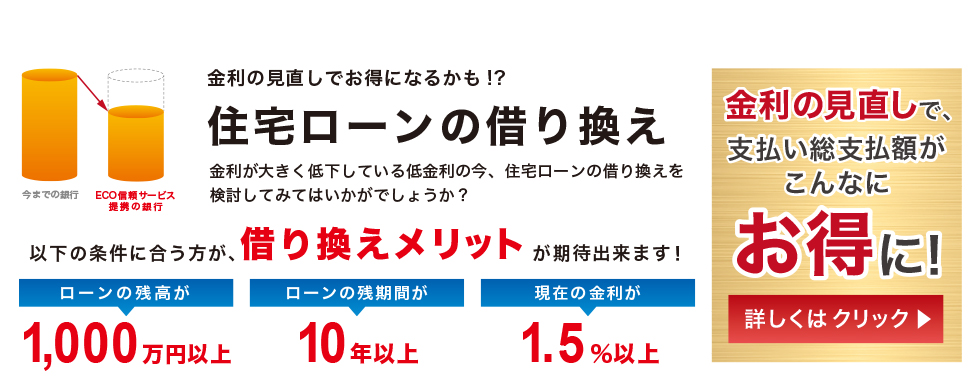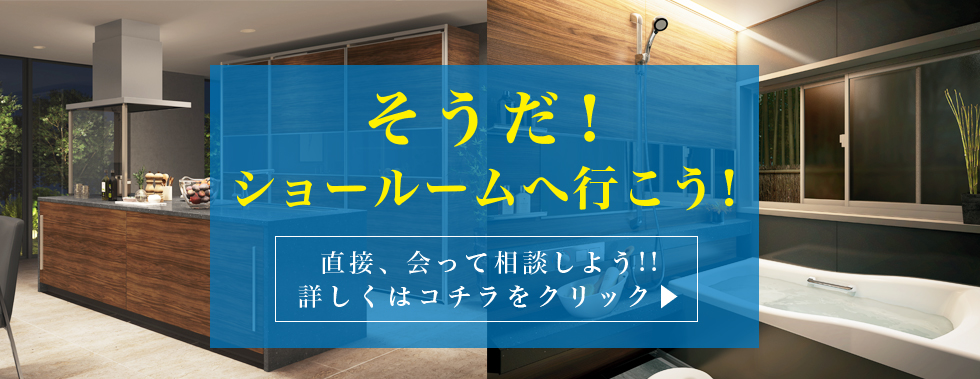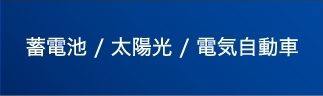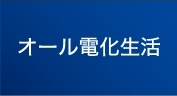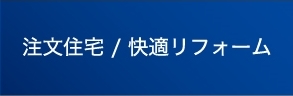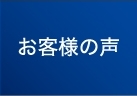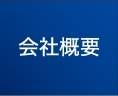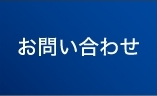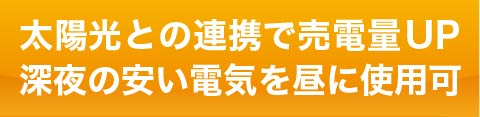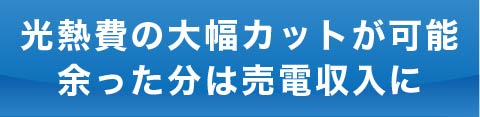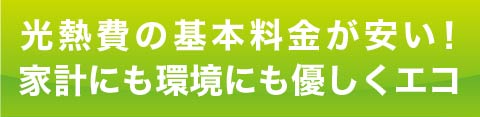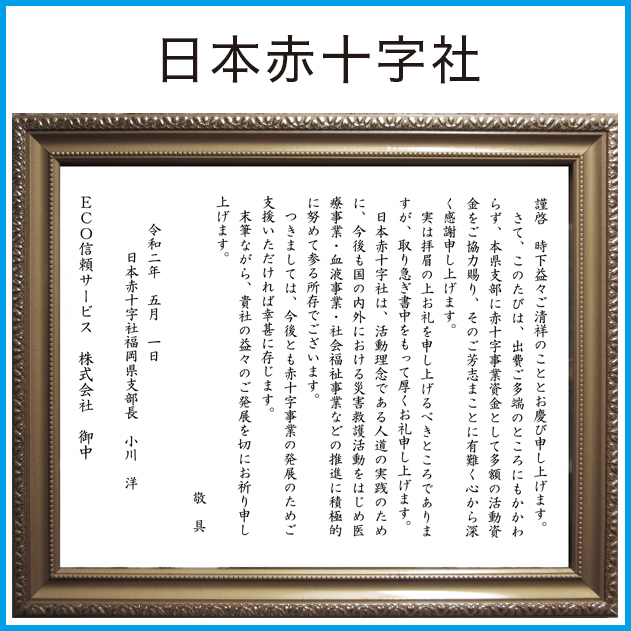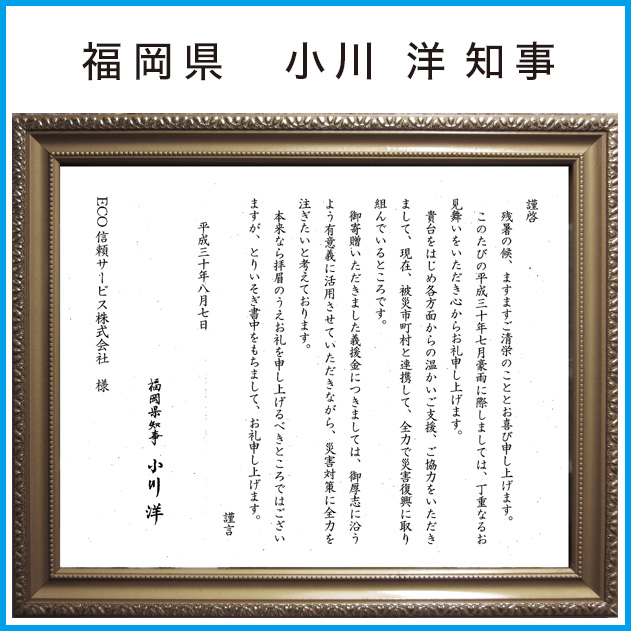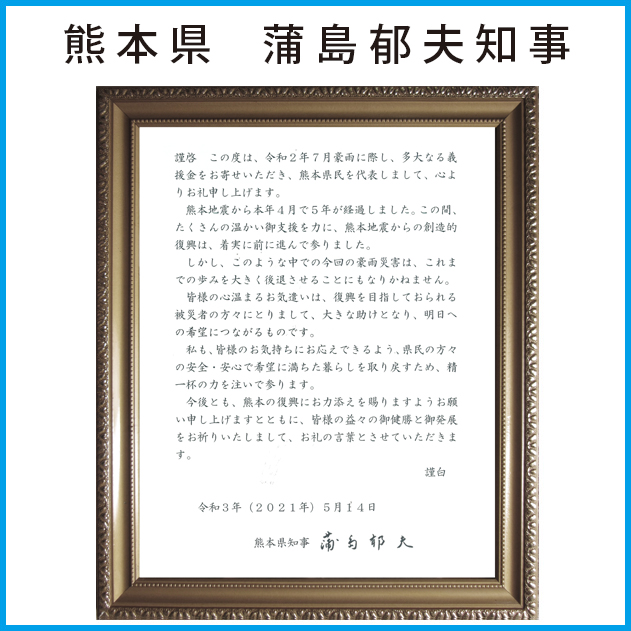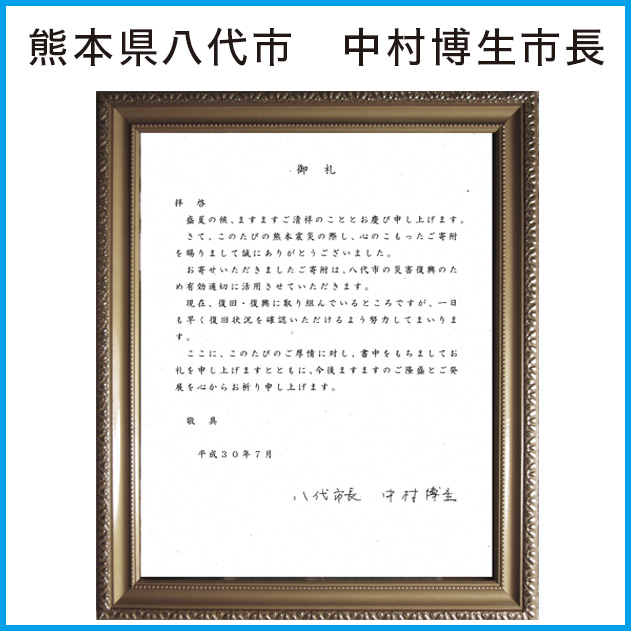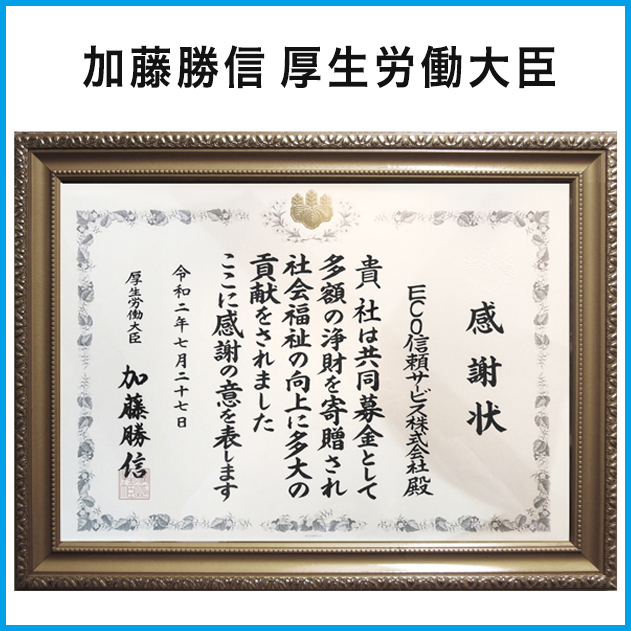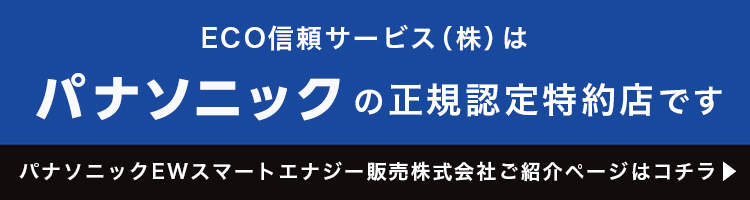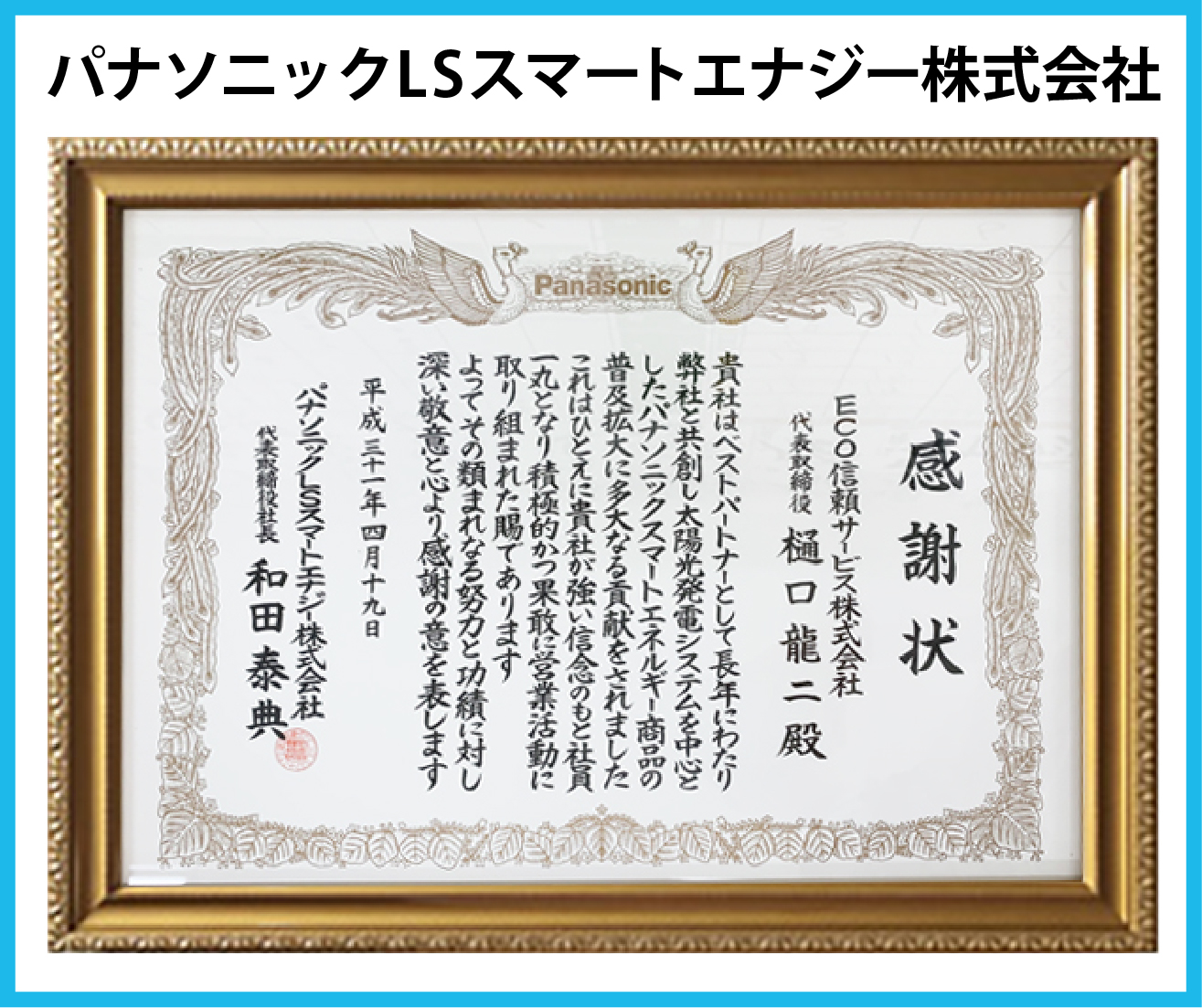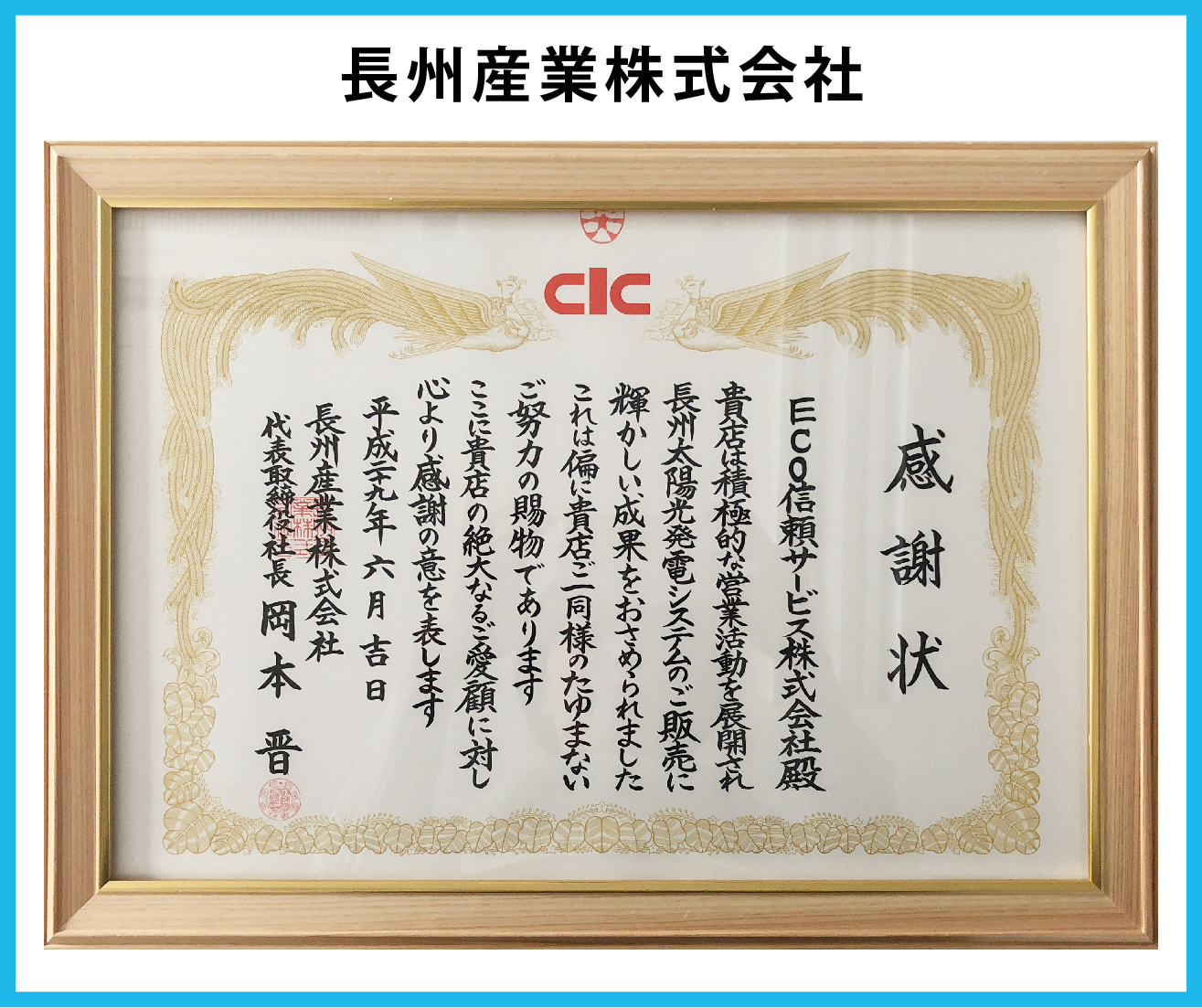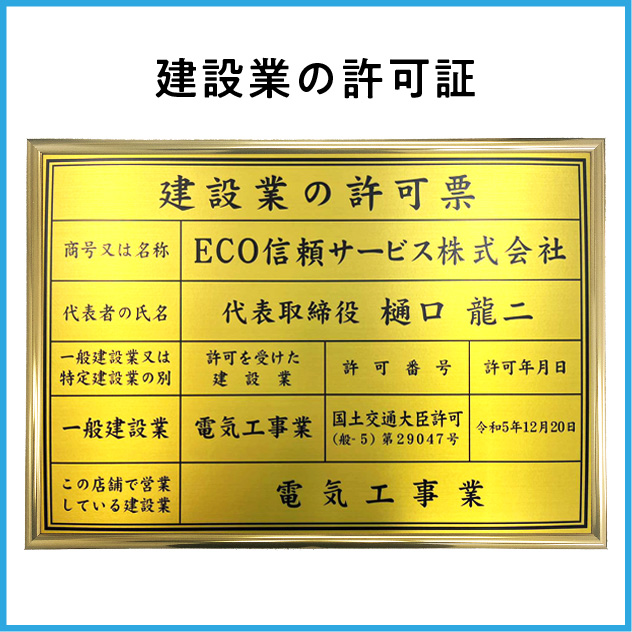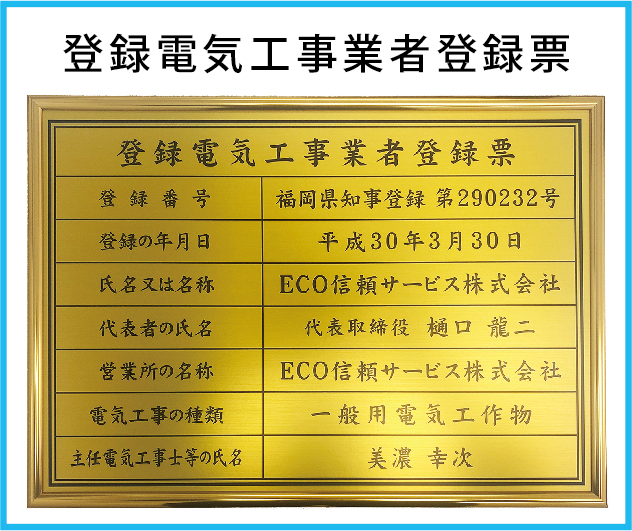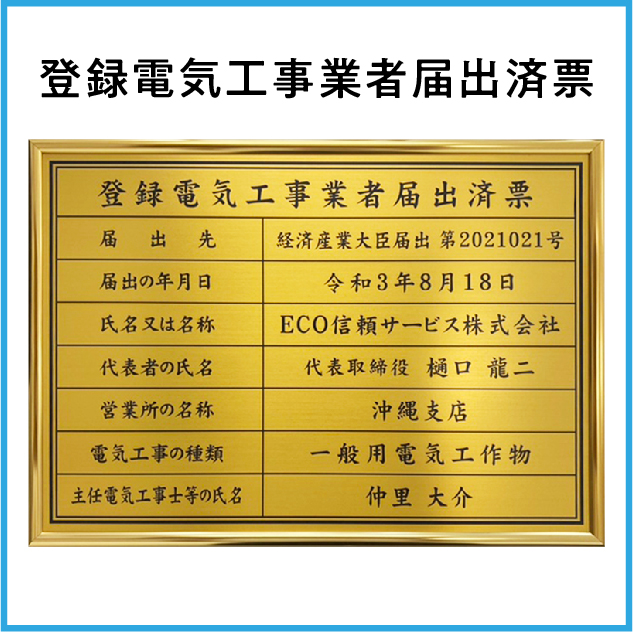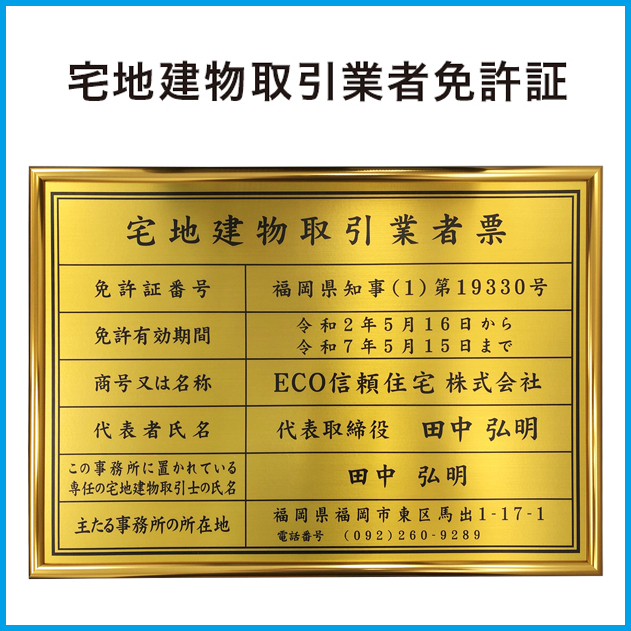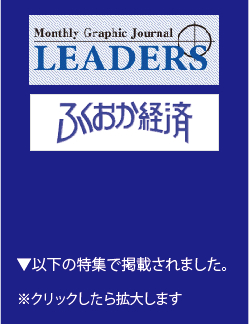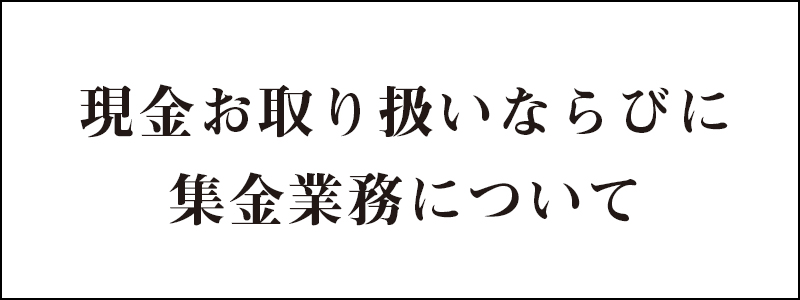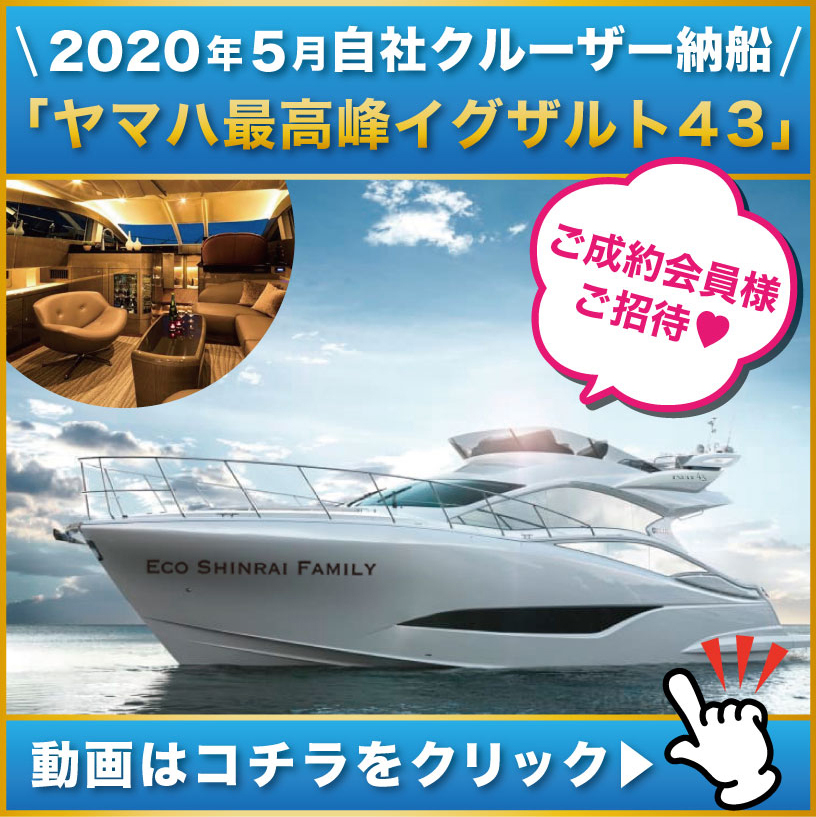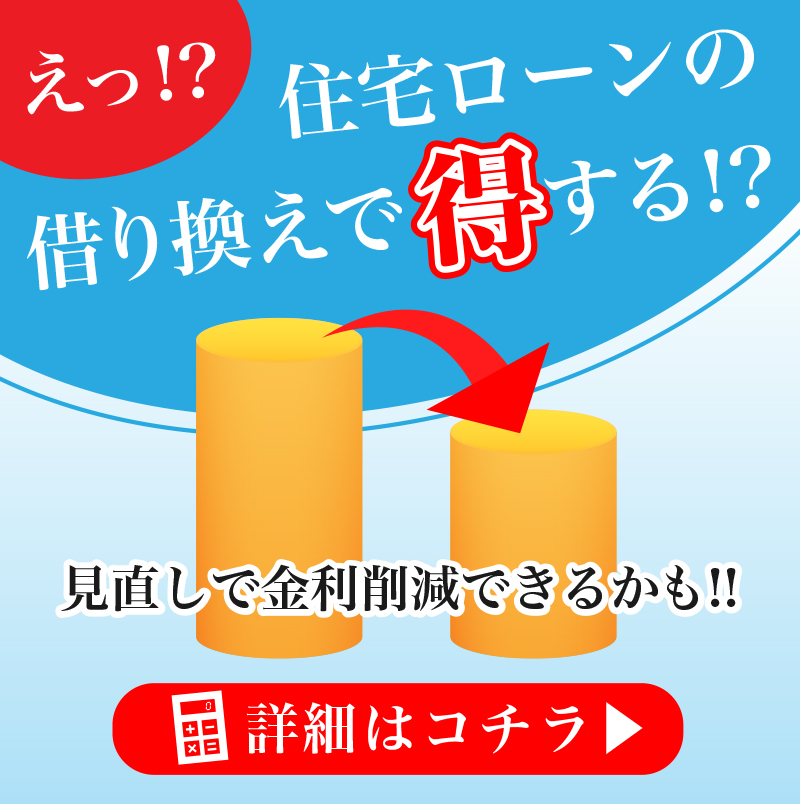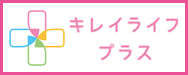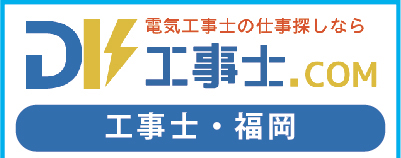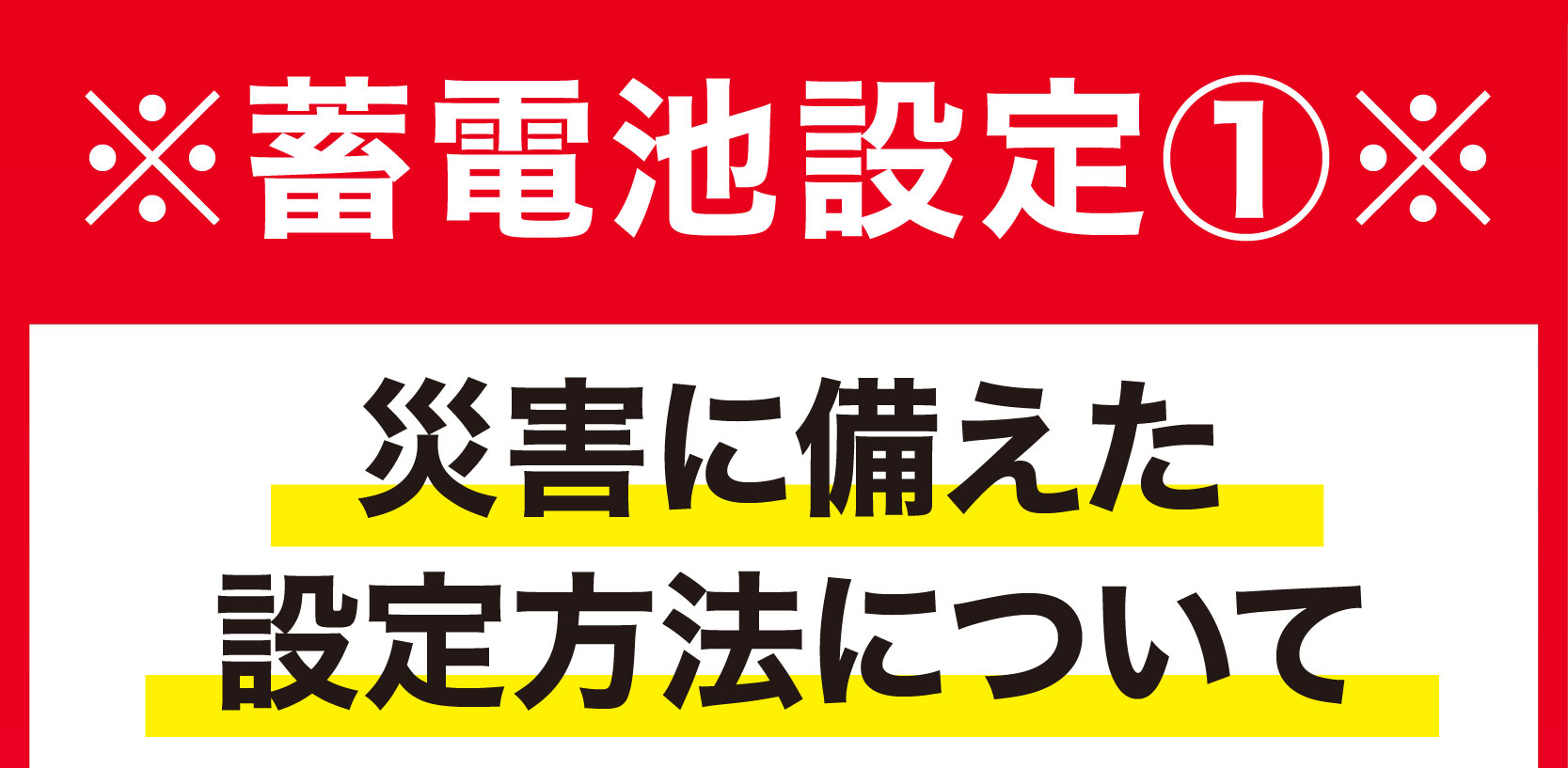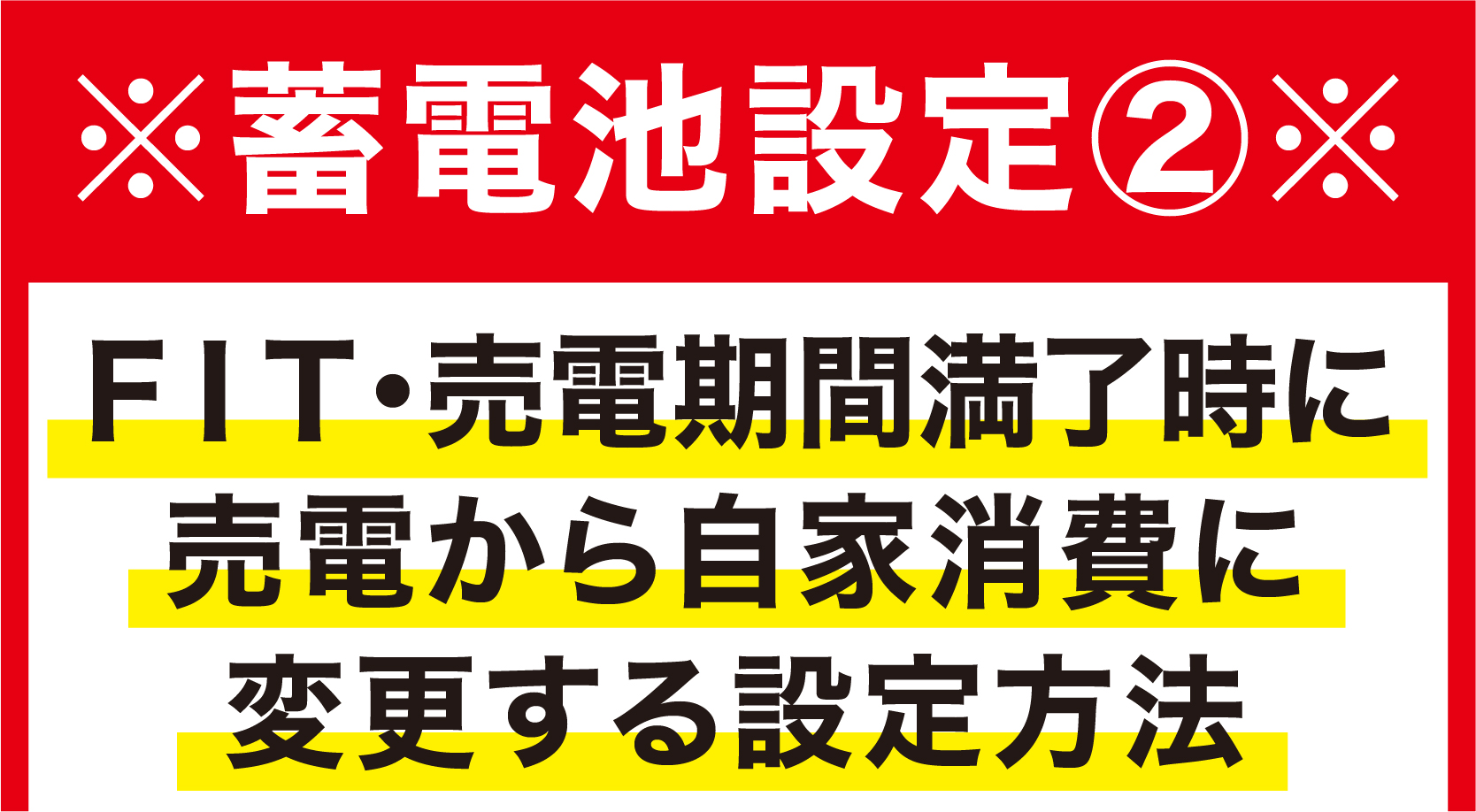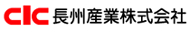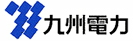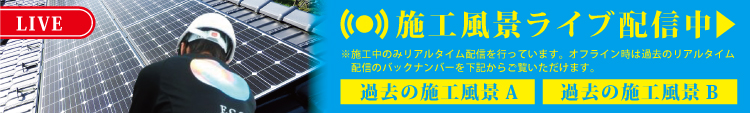

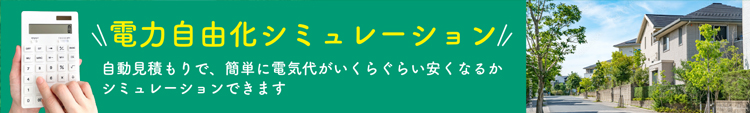



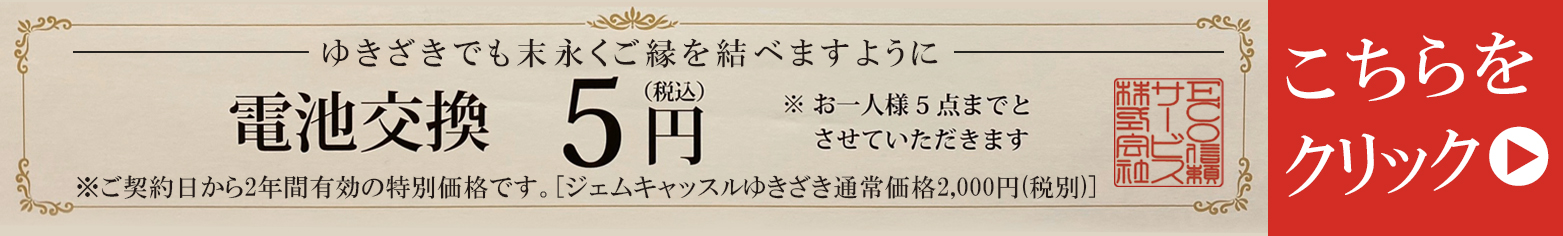


-
2024.07.26
再エネ利用しネイチャーポジティブ実現へ 環境省、実証事業者を募集
環境省は7月23日、2024年度「ネイチャーポジティブとカーボンニュートラルの同時実現に向けた再生可能エネルギー推進技術の評価・実証事業」について、各種技術テーマに取り組む事業者の募集を開始すると発表した。先端的再生可能エネルギー発電事業の検証では、総額1億3500万円以内の予算を組む。
景観への影響がない最先端技術を募集
今回募集するテーマは以下の2つ。
- 国立・国定公園における太陽電池パネル設備の景観評価試験事業
- 自然景観への影響を踏まえてデザインされた先端的再生可能エネルギー発電事業の検証事業
事業の実施期間は、2024年度から2026年度の間の複数年度を前提に、最大3年度。予算としては、景観評価試験事業は総額8500万円以内(3年以内)、先端的再生可能エネルギー発電事業の検証事業は、各年度4500万円以内とし総額1.35億円以内(3年以内)。
まずは、8月29日に事前審査(書類審査)を開始し、10月上旬をめどに、評価審査委員会を開催する。
公募対象者は以下のいずれかに該当する事業者で、共同申請も可能。
- 民間企業
- 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
- 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人・特定非営利活動法人
- 大学
- 国立、または独立行政法人と認められる研究開発機関
- 地方公共団体の研究開発機関
- そのほか、支出負担行為担当官自然環境局長が適当と認める者
自然環境への負荷回避しながら再エネを推進
環境省は現在、再エネ普及によるCO2排出量の削減や吸収源の確保、省エネ対策の地域への実装などの取り組みを推進しているが、ネットゼロ社会の実現には、再エネ施策とともに、サーキュラーエコノミーやネイチャーポジティブの同時に実現が欠かせない。
こうした状況を踏まえ、同省では、目指すべきネイチャーポジティブやネットゼロ社会からバックキャストし、必要となる各種技術テーマについて公募を行い、自然環境への負荷を可能な限り回避し、トレードオフを技術的政策により解消していき、信頼される再エネの推進を目指す同事業を展開している。
記事内容へ -
2024.07.25
中小企業の省エネ支援で新たな連携 金融機関など200を超える組織が参加
経済産業省は7月22日、地域の中小企業の省エネ支援を目的とした「省エネ・地域パートナーシップ」を立ち上げた。地域金融機関や省エネ支援機関など200を超える組織が参加する。
省エネ補助金申請などの優遇措置も
この枠組みにおいて、経産省は、同パートナーシップ事務局とともに、中小企業などの身近な相談先である金融機関や省エネ支援機関などのパートナー機関と、省エネ政策・取り組みなどに関する情報交換を行いながら、省エネを地域で支える施策を展開する。
具体的には、パートナー機関に対し、省エネに関する政策動向の提示に加え、省エネ補助金などの公的支援策、中小企業などで省エネを進める際の着眼点、地域におけるベストプラクティスの共有などの情報を提供する。
また、パートナー金融機関の支援を受けた中小企業などが行う省エネ補助金申請において、優遇措置を行うなど、パートナー機関による省エネ支援の活動を後押しする。
なお、今回参加したパートナー機関は、複数の都道府県を活動地域する金融機関・省エネ支援機関が含まれており、全国をカバーする活動が期待される。
地域間のつながりを強化し、シナジーを発揮
中小企業がエネルギーコスト削減やGXを実行する場合、取り組みの第一歩として、省エネの取り組みが重要となる。
経済産業省はこれまで、企業向けの省エネ支援策として、省エネ診断や省エネ補助金などの支援策を拡充してきた。今回、中小企業などの省エネを地域で支える取り組みを進めるため、同パートナーシップを立ち上げた。
今後は、各地域の関係者のネットワークを強化し、省エネ専門人材の裾野拡大や中小企業などの省エネ促進を通じて、地域の省エネ取り組みを加速させたい考えだ。
記事内容へ -
2024.07.24
東急不、春日部市の公共施設へ再エネ導入 蓄電池併設で災害時利用も
東急不動産(東京都渋谷区)は7月17日、埼玉県春日部市で、市役所以外の公共施設を対象に、PPAを活用した太陽光発電設備を導入すると発表した。2024年度から28年度までの5年間で、約20施設への導入を予定している。
今回、同社は春日部市が保有する公共施設(市役所は対象外)に太陽光発電設備と蓄電池を導入し、運用・維持管理までを担う。震災など非常時には避難所の防災用電源としても活用する。
今回、太陽光発電設備および蓄電池を導入することにより、発電した電力を昼間は施設で使用するほか、余剰分は蓄電池に充電し、夜間や雨天時等は蓄電池の電力を使用できるようにする。対象施設合計で年間約73万3,700kgのCO2排出削減を見込む。
発電した電力の一部は地域の施設等へ供給することで、再エネ電力を最大限地産地消でき、市内の再エネ電力比率向上に貢献するとしている。また、非常時には蓄電池からの電力も活用することで、防災機能の強化を図る。
再エネ導入・地産地消だけでなくレジリエンス向上も
今後同社は、施設の再エネ導入および地産地消の推進のみならず、将来的には特定エリアにおける地域レジリエンス向上を目的とし、既設発電設備とともに災害などで広域停電の際に、小さな地域単位で電力の自給自足ができるようにする「地域マイクログリッド」を構築し、短期的・長期的な視点での脱炭素に向けた取り組みを提案していく。
なお同社は2016年に再生可能エネルギー専任部門を設立。「脱炭素社会の実現」「地域との共生と相互発展」「日本のエネルギー自給率の向上」の3つの社会課題の解決を掲げ、これまでに全国113事業(内訳:太陽光発電94事業、風力発電14事業、バイオマス発電5事業)、定格容量1,763MWの事業に携わってきた(2024年6月末時点)。
さらには全国でエネルギーおよび農業問題の課題解決に向けて2018年より営農型太陽光発電事業に取り組んでいる。2022年12月に運転開始した埼玉県東松山市「リエネソーラーファーム東松山太陽光発電所」のほか、2024年3月には静岡県裾野市でも運転を開始するなど取り組みを全国に広げている。
春日部市においては、2024年1月に「ゼロカーボンシティの実現に向けての連携協定書」を締結しており、営農型太陽光発電を含む同市内での再生可能エネルギーの積極的な導入促進に向けて相互に連携を進めている。
記事内容へ -
2024.07.23
スズキ、四輪車の技術戦略を発表 コンパクトな車づくりでエネルギー極小化へ
スズキ(静岡県浜松市)は7月17日、技術戦略説明会を開催し、10年先を見据えた四輪車の技術戦略を発表した。
「軽くて安全な車体」「バッテリーリーンなBEVとHEV」「効率の良いICEとCNF技術の組み合わせ」「SDVライト」「リサイクルしやすい易分解設計」の5つの柱に、製造からリサイクルまで、エネルギー消費を最小限に抑える技術の実現を目指す。
コンパクトな車づくりを得意とする同社は、「小・少・軽・短・美」をコンセプトに、走行時のCO2排出量や製造過程で排出するCO2を抑える車づくりを通じて、環境負荷軽減の取り組みを推進してきた。
同社は今回、車が小さければ、製造に必要となる資材やエネルギー消費を抑えることができるという考え方を重視するとともに、レアアース、レアメタルなどの資源リスクや道路整備負担の軽減や車両そのもののリサイクル負担の軽減の観点から、エネルギーの極少化を掲げた。
電気自動車(BEV、HEV)については、2035年に日本はハイブリッドを含め100%新車販売が、HEVが7割、BEV3割、インドはHEV、BEVがほぼ3分の1ずつ、欧州では全量がBEVになると予想。
また、ライフサイクル(車の材料となる資源採掘、部品や製造に必要なエネルギー、車を走らせるために必要なエネルギー、廃棄・リサイクルまで、車の生涯にわたり必要な2次エネルギー)については、BEVのエネルギー消費量がHEV車のそれを下回るためには、「非化石燃料化石燃料による電気エネルギーが75%が必要」という試算結果も発表した。
地域と時期を見て、BEV、HEV、あるいはカーボンニュートラル燃料を使う内燃機関とするなど、技術のラインアップのマルチパスウェイ化が必要との考えを示した。
記事内容へ -
2024.07.18
NTTドコモ(東京都千代田区)、NTTアノードエナジー(同・港区)、NTTスマイルエナジー(大阪府大阪市)のNTTグループ3社は8月1日、家庭用蓄電池を最適制御する実証実験を開始する。 実証では、家庭用蓄電池を活用し、蓄電池を制御・集約するリソースアグリゲーションなどを行い、日中時間帯に発電量が過剰となりやすい太陽光発電に合わせた電力使用を実現する。これにより再エネの有効活用を目指す。期間は2025年2月28日までの約7カ月間。
この実証は、NTTドコモが提供する電力サービス「ドコモでんき」の契約者で、NTTスマイルエナジーが提供する家庭の太陽光発電と蓄電池に対応した遠隔監視サービス「ちくでんエコめがね」の契約者を対象に行う。
需給がひっ迫している時間帯に向けて、家庭用蓄電池の充電・放電のタイミングを遠隔かつ最適に制御し、サービスの事業性などを検証する。検証項目として、蓄電池1台当たりの経済メリットと、実証の顧客満足度を挙げている。
3社は今後、この実証にて得られた知見やデータをもとに各社のリソースやノウハウを生かすことで、「ドコモでんき」と「太陽光発電・蓄電池を利用した家庭向けエネルギーサービス」を組み合わせたコンシューマー向けサービスの提供など、エネルギー分野での新規事業の検討をはじめとする社会全体の脱炭素化の実現に向けた取り組みを検討していく。
また、3社は同日、全国の「ドコモでんき」契約者かつ「ちくでんエコめがね」契約者を対象に、実証に参加する顧客の募集を開始した。期間は11月30日までの予定。
実証に参加する顧客には、参加特典として、NTTドコモが提供するポイントプログラム「dポイントクラブ」のdポイント1万ポイント(期間・用途限定)を進呈するほか、制御後の電力購入量について、直近の平均電力購入量から減少した1kWhあたりdポイント5ポイント(期間・用途限定)を進呈する。顧客は、普段通り過ごすだけでdポイントを受け取ることができる。
記事内容へ

-
- 福岡県福岡市F発電所 様
- 125.781kw
- 沖縄県那覇市N発電所 様
- 122.659kw
- 熊本県玉名市T発電所 様
- 109.332kw
2024年7月