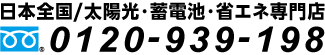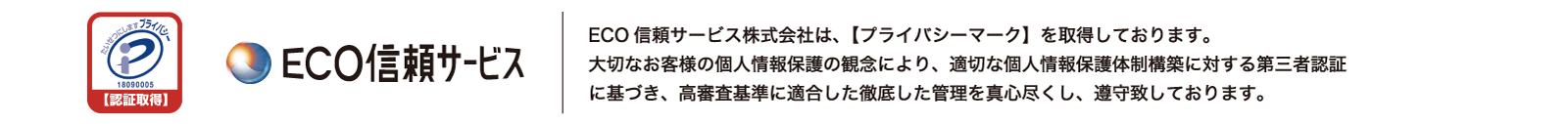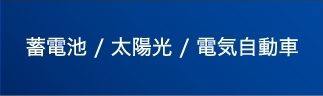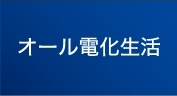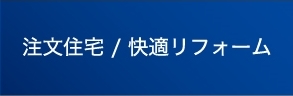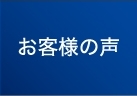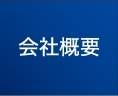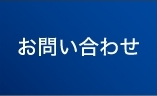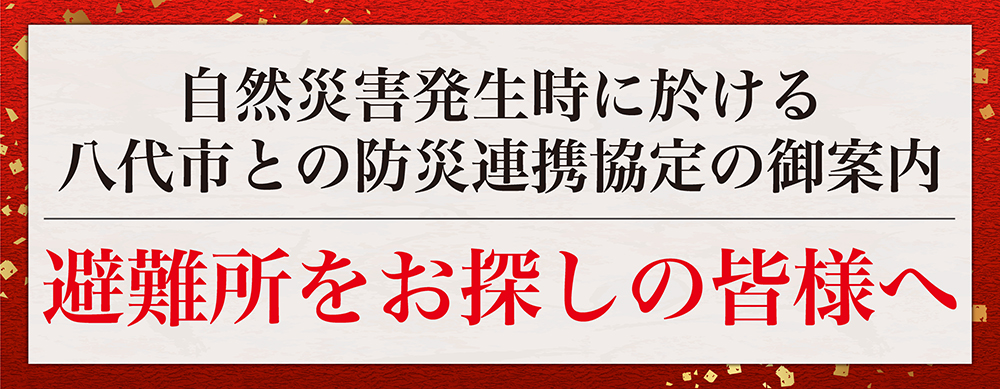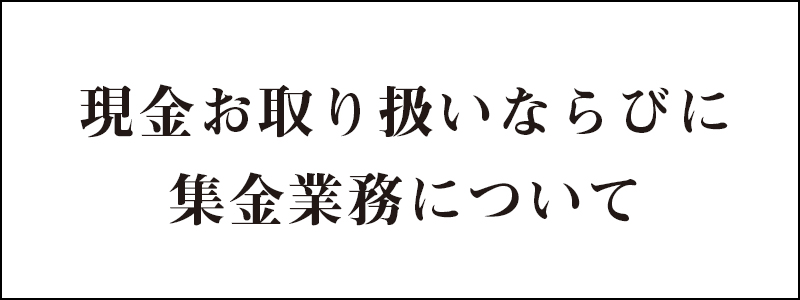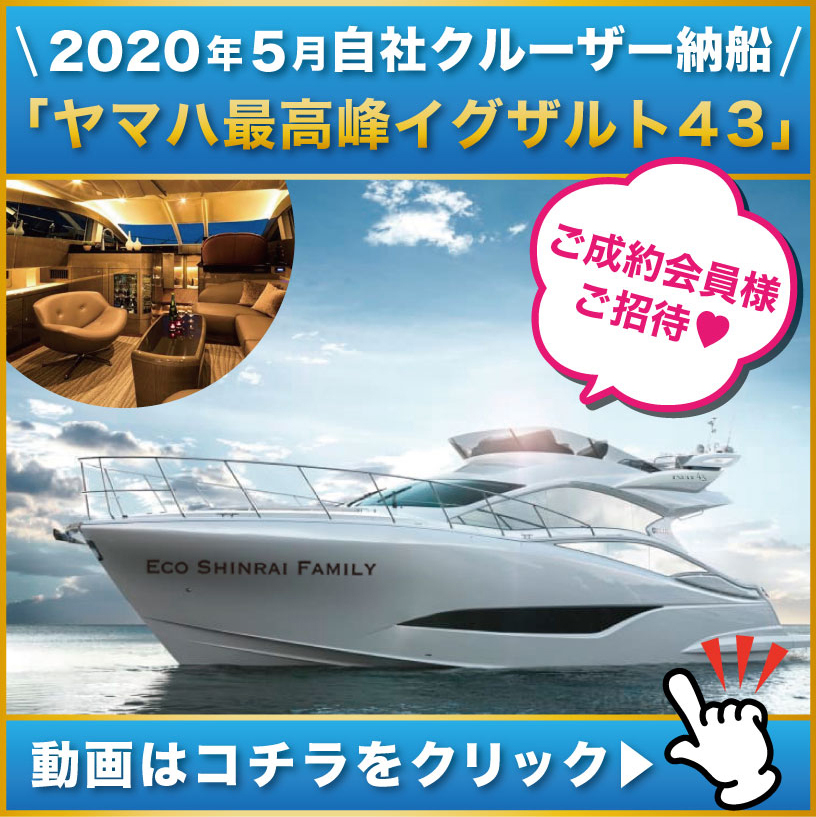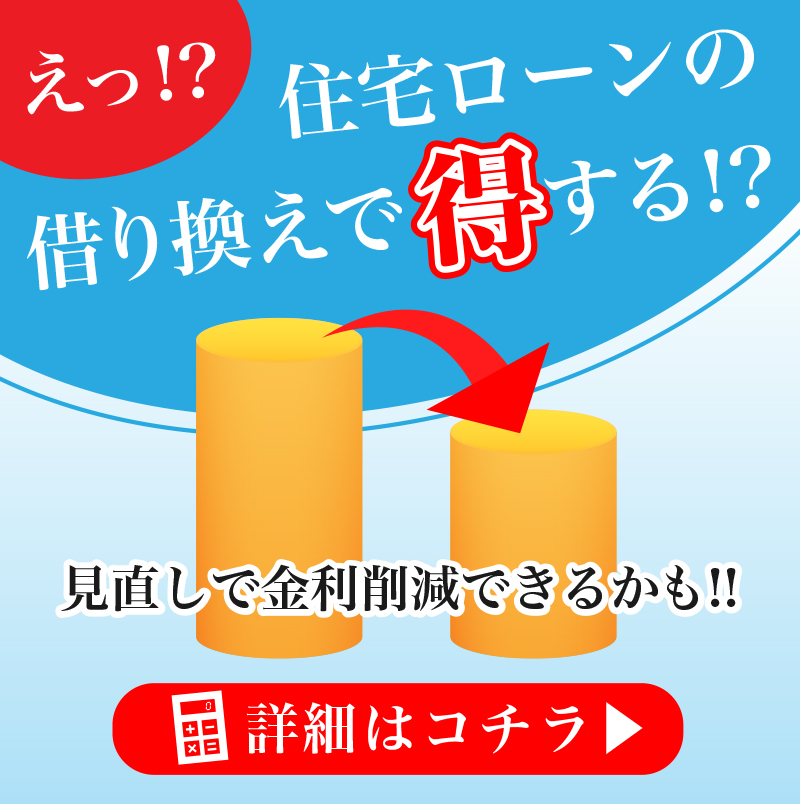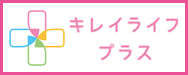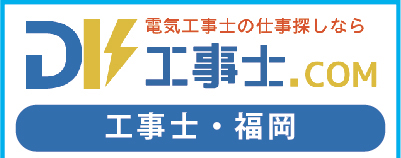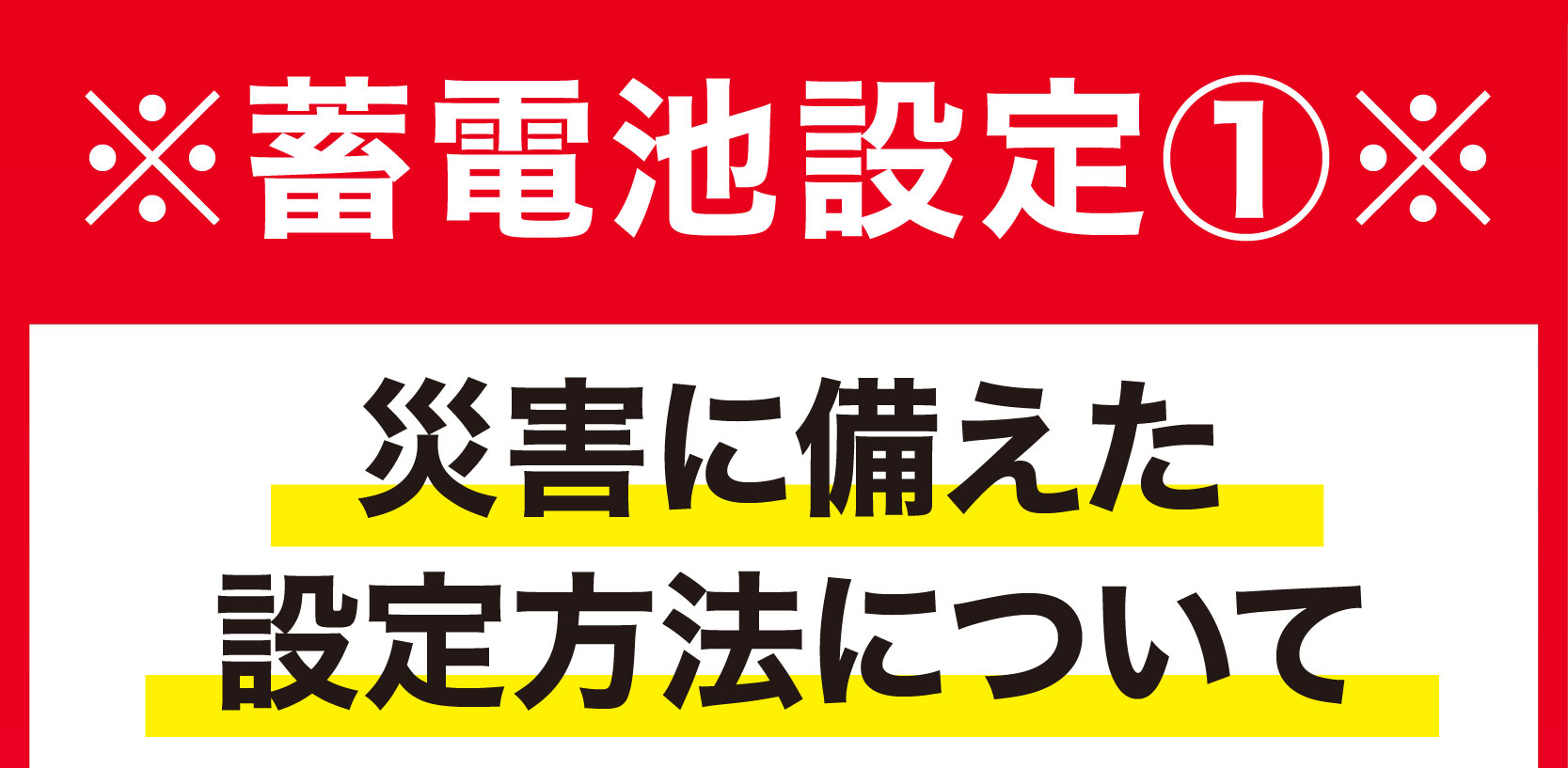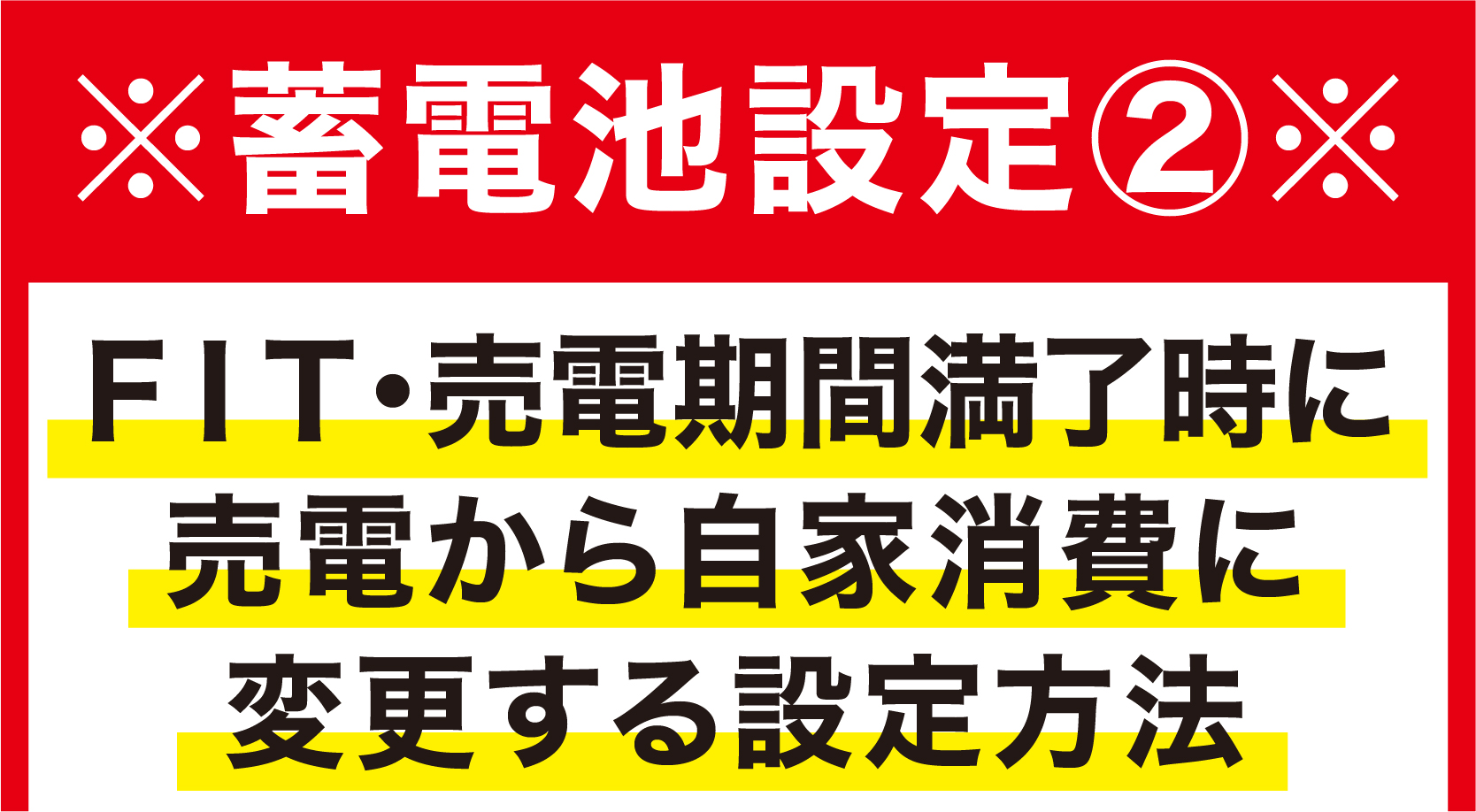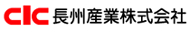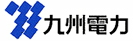- ホーム
- インフォメーション
-
2023.09.13
トヨタ、米・物流拠点でグリーン水素生成施設が竣工 港湾オペCN実現へ
トヨタ自動車(愛知県豊田市)は9月7日、北米事業体であるToyota Motor North Amerが、米国カリフォルニア州ロングビーチ港の物流拠点トヨタロジスティクスサービス(TLS)において、グリーン水素をオンサイトで生成する施設「Tri-Gen(トライジェン)」を竣工したと発表した。これにより、100%再生可能エネルギー由来のカーボンニュートラル(CN)な港湾オペレーションの実現を目指す。
Tri-Genは、燃料電池発電事業を手がける米国FuelCell Energy社が運営する。2.3MWの発電が可能な燃料電池発電所と水素ステーションを併設。畜産場の家畜排泄物や余剰食品等の廃棄物系バイオマスから水素を取り出し、燃料電池を用いて発電することで、再エネから水素・電気・水の3つ(Tri)の物質を生成(Generate)する。
記事内容へ -
2023.09.12
福岡県直方市、再エネ電力を汚泥処理センターに導入 オンサイトPPA活用
西鉄自然電力合同会社(福岡県福岡市)と北九州パワー(同・北九州市)は9月6日、 福岡県直方市の汚泥再生処理センター「クリーンHitzのおがた」において、オンサイトPPAによる再エネ電力の供給を開始したと発表した。今回の取り組みは、同市の公共施設におけるPPA第1号案件となる。
年間約191MWhを発電予定
クリーンHitzのおがたには今回、屋上部分に344枚の太陽光パネルが設置された。
記事内容へ -
2023.09.11
中部電力・bp、名古屋港で排出されたCO2をインドネシアに貯留 調査開始
中部電力(愛知県名古屋市)は9月11日、英石油大手bpの子会社であるBP Berau(BPベラウ)と、名古屋港で排出されたCO2の貯留先として、インドネシア・西パプア州の「タングーCCUSプロジェクト」のCO2貯留地を活用する実現可能性について、調査を行うと発表した。
BPベラウは、インドネシア最大のガス生産プロジェクト「タングーLNG」のオペレーターで権益保有者の代表。bpがタングーLNGにおいて運営する「タングーCCUSプロジェクト」は、2021年に同国政府より承認を受けた開発計画に基づき基本設計が進められている。同国で最も進んだCCUS(CO2回収・有効利用・貯留)プロジェクトである。貯留可能量は約18億t-CO2で、同国初のCCSハブになる可能性がある。
記事内容へ -
2023.09.10
パイオニアとNextDrive、「EV充放電制御システム」開発で協業
パイオニア(東京都文京区)は9月6日、エネルギー管理とクラウドサービスの開発・提供を行うNextDrive(同・港区)と協業し、電力データと車両の移動データを掛け合わせることによりEV関連のエネルギーマネジメントを最適化する「EV充放電制御システム」を開発すると発表した。これにより、EV導入事業者の運用効率化と電力コスト削減に取り組む。
協業においてパイオニアは、車両の移動データを収集し、独自のプラットフォーム「Piomatix for Green(パイオマティクス・フォー・グリーン)」を活用してEVのSoC(State of Charge:充電状態)や消費電力量を予測する。NextDriveは、同社のエネルギーマネジメントコントローラー/IoE ゲートウェイ「Atto(アット)」を活用した電力データ収集およびEV充電機器やV2H機器の操作を担当する。
記事内容へ -
2023.09.09
スズキ、インドで牛ふん由来のバイオガスから自動車燃料を精製 実証開始へ
スズキ(静岡県浜松市)は9月6日、インドにおいて、牛ふんが発酵することで発生するバイオガスから、自動車用燃料となるメタンを精製する実証事業を開始すると発表した。実証に向けて2025年以降、4つのバイオガス生産プラントを設置する。
同社は実証開始にあたり、スズキ100%出資のSuzuki R&D Center Indiaを通じて、インドのNational Dairy Development Board(NDDB/全国酪農開発機構)、インド乳業メーカー大手のBanas Dairyと相互連携していくことで合意した。
精製する燃料はCNG仕様車の燃料として販売
記事内容へ -
2023.09.08
クボタ、石油化学プラント用反応管の生産ライン増強へ
クボタ(大阪府大阪市)は9月5日、石油化学プラント用の反応管の生産能力を増強すると発表した。反応管の主力工場である枚方製造所に生産ラインを増設し、同拠点における年間生産能力を現在の約180%に引き上げる。
アジア・北米で石油化学プラントの建設・更新需要が増加
投資額は約44.5億円。各設備は設置が完了次第、順次増産に向けて稼働を開始する。全設備の稼働は2026年4月を予定している。
記事内容へ -
2023.09.07
世界初・バイオPX製造、サントリーのペットボトル原料に活用 24年開始
ENEOS(東京都千代田区)、三菱商事(同)、サントリーホールディングス(同・港区)の3社は9月4日、バイオパラキシレン(バイオPX)を原料としたサステナブルPRT樹脂のサプライチェーン構築で協業を開始すると発表した。
約3500万本分のバイオPXを製造
3社は今後、商業規模で世界初となるバイオPXを製造することで、ペットボトル原料となるPET樹脂主原料のひとつである高純度テレフタル酸(PTA)のバイオ化を目指す。
記事内容へ -
2023.09.06
ホンダ、新型・可搬型外部給電器を発売 EV接続で給電可
本田技研工業(東京都港区)は9月1日、電動車両(BEV・FCEV・PHEV)と接続することでさまざまな電化製品に電気を供給できる可搬型外部給電器の新型「Power Exporter e: 6000」の販売を、全国のHonda Carsで開始した。価格は88万3960円(税込)。
最大6kVAの電力を出力、車載搭載も容易に
新型の給電器は、ポータブル発電機の開発で培った、同社独自の正弦波インバーター技術を採用。精密機器や楽器など、電気の質が求められる製品にも対応する高品質な電力の供給が可能な可搬型外部給電器の従来製品「Power Exporter 9000」に改良を加えた新タイプだ。
記事内容へ -
2023.09.05
パナソニックHD、「発電するガラス」の技術検証開始 建材一体型の太陽電池
パナソニックホールディングス(パナソニックHD/大阪府門真市)は8月31日、ガラス建材一体型ペロブスカイト太陽電池のプロトタイプを開発し、神奈川県藤沢市に新設されたモデルハウスにて、同素材の技術検証を開始したと発表した。同検証は2024年11月29日までで、約1年以上の長期にわたって実施される予定だ。
長期設置による発電性能や耐久性などを検証
今回の実証では、モデルルーム2階バルコニー部分に、グラデーション状の透過型のペロブスカイト太陽電池を配置。目隠し性と透光性を両立させたデザインとともに、長期設置による発電性能や耐久性などを検証する。
記事内容へ -
2023.09.04
日立ソリューションズ、製造業のサプライチェーン脱炭素化を支援
日立ソリューションズ(東京都品川区)は8月31日、「サプライチェーン脱炭素支援ソリューション」の提供を開始した。製造業の脱炭素に向けて、課題抽出から、製品・企業・サプライチェーンにおけるCO2排出量の把握や予測、ESGにおけるサプライヤーの評価まで、先進的で実績ある欧米や日本の5つの製品・サービスでトータルに支援する。
その一環として、Makersite GmbH(ドイツ シュトゥットガルト)と日本初の販売代理店契約を締結した。同社は、製品やサプライチェーンのCO2排出量を高精度かつ詳細に自動報告や分析を行うことで大規模な脱炭素化を支援する、AIを用いた製造業向け製品ライフサイクルソフトウェア「Makersite」を提供する。
記事内容へ